
住宅ローンの返済が難しくなり任意売却を検討している中で、「抵当権」という言葉を目にして不安になっていませんか?
「抵当権が付いたままだと家は売れないの?」「手続きが複雑そう…」といった疑問や不安を抱えるのは当然のことでしょう。
この記事では、任意売却と抵当権の基本的な関係から、抵当権を抹消して無事に売却を終えるまでの流れ、そして失敗しないための注意点まで、専門用語をかみ砕きながら分かりやすく解説していきます。
まずは基本から|任意売却と抵当権のキホン

ここでは、任意売却を理解する上で欠かせない「抵当権」の基本的な意味と、なぜ任意売却で重要になるのかを解説していきます。
抵当権とは?住宅ローンとセットで設定される権利
抵当権とは、住宅ローンを借りる際に、購入した不動産に設定される担保の権利のことです。
簡単に例えると、友人にお金を貸すときに「返せなかったら、あなたの大切な時計を私がもらう約束にしよう」と決めるようなものでしょう。銀行も同じように、数千万円という大きなお金を貸すとき、「返済できなくなったら、この家を売って返済にあてる権利をください」と約束するのが抵当権なのです。
この権利は法務局に登記されるため、誰でも確認できる公的な記録として残ります。住宅ローンを完済するまで、この抵当権は不動産に付いたままになっています。
任意売却とは?競売を避けるための売却方法
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった際に、競売にかけられる前に自分の意思で不動産を売却する方法です。競売では市場価格の6〜7割程度でしか売れないことが多いのに対し、任意売却なら市場価格に近い金額での売却が期待できるでしょう。
さらに、競売では強制的に退去日が決められてしまいますが、任意売却では買主との交渉により、引っ越し時期をある程度調整することも可能になります。
精神的な負担も大きく異なり、競売では近所に知られてしまう可能性が高いものの、任意売却なら通常の不動産売却と同じように進められるため、プライバシーも守られます。
最重要ポイント!任意売却では「抵当権の抹消」が必須
任意売却を成功させるためには、必ず抵当権を抹消しなければなりません。なぜなら、抵当権が付いたままの不動産を購入したいと思う人はいないからです。
購入者の立場で考えてみると分かりやすいでしょう。もし抵当権が残ったまま不動産を購入した場合、前の所有者のローンが返済できなくなったとき、自分が住んでいる家が競売にかけられてしまう可能性があるのです。
そのため、不動産の売買では「所有権移転」と「抵当権抹消」を同時に行うことが基本的なルールとなっています。任意売却においても、売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消してから買主に所有権を移すという流れが必要になります。
任意売却で抵当権を抹消する5つのステップ

実際に抵当権を抹消して任意売却を進めるための具体的な流れを、5つのステップに分けて時系列で解説します。ご自身の状況がどの段階にあるのかを確認しながら読み進められる構成になっています。
ステップ1:債権者(金融機関)へ相談し、任意売却の同意を得る
任意売却を始める前に、まず住宅ローンを借りている金融機関(債権者)に相談し、任意売却への同意を得る必要があります。
この段階では、現在の返済状況や家計の収支を正直に伝え、今後の返済が困難であることを説明しましょう。金融機関としても、競売よりも任意売却の方が回収できる金額が多くなることを理解しているため、誠実に対応すれば協力してもらえるケースがほとんどです。
具体的には、任意売却の期間(通常3〜6ヶ月程度)や、売却活動を行う不動産会社についての相談を行います。金融機関によっては、信頼できる不動産会社を紹介してくれることもあるでしょう。
ステップ2:不動産会社と共に売却活動を開始する
債権者の同意を得た後は、任意売却に精通した不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。
売却価格の設定は、債権者との協議により決定されることになります。市場価格を参考にしながらも、債権者が納得できる金額である必要があるため、通常の売却よりも慎重に価格設定を行う必要があるでしょう。
販売活動では、インターネットでの物件掲載や住宅情報誌への掲載、現地見学会の開催など、通常の不動産売却と同様の手法が用いられます。ただし、売却期間には制限があるため、効率的な販売戦略が重要になってきます。
ステップ3:購入希望者を見つけ、売買契約を結ぶ
購入希望者が現れたら、売却価格や条件について交渉を行います。この際、最終的な売買価格については債権者の承認が必要になるため、購入希望者にはその旨を説明しておくことが重要でしょう。
債権者が売買価格に同意したら、正式に売買契約を締結します。通常の不動産売買と同様に、手付金の授受や引き渡し日の設定などを行いますが、任意売却の場合は抵当権抹消の手続きも含めたスケジュール調整が必要になります。
契約書には「抵当権抹消を条件とする」旨の特約を記載することで、万が一抵当権が抹消できない場合の対処法も明確にしておくことが大切です。
ステップ4:売買代金の決済と配分案の調整
不動産の引き渡し日には、売買代金の決済と同時に抵当権抹消の準備を行います。
売却代金がローン残高を下回るケース(オーバーローン)では、配分案の調整が必要になるでしょう。複数の債権者がいる場合は、それぞれの債権額に応じて配分を決める必要があります。また、不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬なども、この配分の中から支払われることになります。
金融機関との最終的な配分合意が得られたら、決済当日に向けて抵当権抹消に必要な書類の準備を進めます。
ステップ5:司法書士が法務局で抵当権抹消登記を行う
決済当日は、買主からの代金支払いと同時に、司法書士が法務局で抵当権抹消登記の手続きを行います。
この手続きでは、債権者から提供される「抵当権設定契約証書」「委任状」「弁済証書」などの書類を用いて、正式に抵当権を抹消する登記を行うのです。同時に、買主への所有権移転登記も実施され、これによって任意売却が完了することになります。
登記手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的でしょう。費用は売却代金から支払われるため、売主が事前に用意する必要はありません。
失敗しないために|抵当権に関する任意売却の3つの注意点

任意売却をスムーズに進めるために、特に注意すべき専門的なポイントを3つに絞って解説します。
注意点1:抵当権者が複数いる場合は全員の同意が必要
住宅ローン以外にも、リフォームローンやカードローンなどの担保として、第二抵当権や第三抵当権が設定されているケースがあります。
この場合、すべての抵当権者から任意売却への同意を得る必要があるでしょう。特に後順位の抵当権者(第二抵当権者など)は、売却代金から受け取れる金額が少なくなる可能性が高いため、同意を得るのが困難になることがあります。
このような場合は「ハンコ代」と呼ばれる解決金を支払うことで、抵当権抹消への協力を得ることが一般的です。金額は数十万円程度になることが多く、先順位の債権者が負担するケースが多いでしょう。
注意点2:税金の滞納による「差押え」が入っている場合
住宅ローンの返済が困難になると、固定資産税や住民税なども滞納してしまうケースが少なくありません。
税金を滞納すると、市町村や国税局によって不動産に「差押え」の登記がされることがあります。この差押えは抵当権とは別の権利ですが、不動産売却の際には同様に解除する必要があるのです。
差押えの解除には、滞納税額の完納または分割納付の約束が必要になります。任意売却の際は、売却代金から税金を支払うことで差押えを解除してもらう交渉を行うことになるでしょう。
注意点3:抵当権の抹消にかかる費用は誰が負担する?
抵当権抹消にかかる費用は、原則として売却代金から支払われることになります。
具体的な費用としては、登録免許税(不動産1個につき1,000円)と司法書士への報酬(5〜10万円程度)が必要です。これらの費用は配分案の作成時に考慮されるため、売主が事前に現金を用意する必要はありません。
ただし、売却代金が少ない場合は、これらの費用を確保するために売却価格の調整が必要になることもあるでしょう。債権者との交渉では、抵当権抹消費用も含めた総合的な配分を検討することが重要になります。
任意売却と抵当権のよくある質問(Q&A)
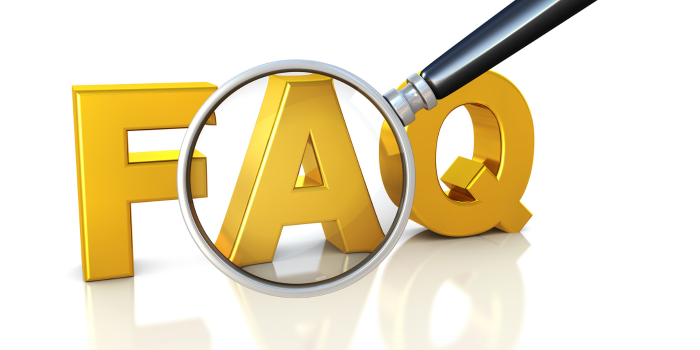
これまで説明した内容以外に、読者が抱きやすい具体的な疑問についてQ&A形式で回答します。
Q. 抵当権者である金融機関が、任意売却に同意してくれないことはありますか?
A. 金融機関が任意売却に同意しないケースは稀ですが、全くないわけではありません。
同意が得られない主な理由としては、債務者の対応が不誠実だった場合や、提案された売却価格が著しく低い場合などが挙げられるでしょう。また、既に競売手続きが進んでいる場合は、タイミング的に任意売却が困難になることもあります。
このような場合は、任意売却に精通した不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、金融機関との交渉を代行してもらうことが効果的です。第三者が入ることで、冷静な話し合いができるようになることが多いでしょう。
Q. 任意売却後、残ってしまった住宅ローンはどうなるのでしょうか?
A. 抵当権は抹消されますが、残ったローンの返済義務はなくなりません。
売却代金でローンを完済できない場合(オーバーローン)は、残った債務を「無担保債権」として返済していくことになります。金融機関との話し合いにより、月々の返済額を家計の状況に応じて減額してもらうことが一般的でしょう。
多くの場合、月1〜3万円程度の無理のない金額での分割返済が認められます。完済までの期間は長くなりますが、競売と比べて残債務を大幅に減らせるため、その後の生活再建がしやすくなるのです。
Q. 手続きはすべて自分一人で進めなければいけませんか?
A. 任意売却の手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、一人で進めるのは現実的ではありません。
通常は、任意売却に精通した不動産会社が窓口となり、債権者との交渉から買主探し、司法書士や税理士などの専門家との連携まで、トータルでサポートしてくれます。また、法律的な問題が複雑な場合は、弁護士に相談することも重要でしょう。
これらの専門家への報酬も、基本的には売却代金から支払われるため、手元に資金がなくても手続きを進めることができます。一人で抱え込まず、まずは信頼できる専門家に相談することが成功への近道なのです。
まとめ:抵当権が関わる任意売却は、早めに専門家へ相談を
任意売却における抵当権の抹消は、複数の関係者との調整や専門的な手続きが必要な複雑なプロセスです。債権者との交渉、配分案の作成、登記手続きなど、一般の方が一人で対応するには限界があるでしょう。
重要なのは、住宅ローンの返済が困難になった段階で、できるだけ早く行動を起こすことです。競売の手続きが開始されてからでは選択肢が限られてしまうため、まだ余裕があるうちに任意売却の検討を始めることが賢明といえます。
任意売却の実績が豊富な不動産会社や、不動産法務に詳しい法律の専門家に相談することで、抵当権の問題もスムーズに解決できるはずです。一人で悩まず、まずは専門家に相談することが、より良い条件での解決につながる第一歩になるでしょう。

