相談者様のプロフィール
小林美佳さん(仮)、52歳、神奈川県藤沢市在住。
地方銀行事務職として28年勤務、年収420万円。夫(54歳・製造業管理職)、長女(26歳・看護師・既婚)、次女(24歳・大学院生)の4人家族。
母(78歳・認知症初期)の介護を一人で担っている。兄(55歳・IT企業役員・独身)は東京都港区在住で、月に一度実家を訪れる程度。
ご相談の内容
美佳さんの父が3年前に亡くなった際、兄の健太郎さんが相続手続きを主導し、「母の介護費用として残しておこう」との提案で手続きを先延ばしにしていました。しかし先月、銀行の同僚から「お兄さん、10年前にお父さんから1,000万円もらってマンション買ったって聞いたけど」と言われ、事実を確認すると、健太郎さんは大学院進学時の学費500万円、マンション購入資金1,000万円、起業資金300万円の計1,800万円を生前贈与として受け取っていたことが判明しました。
一方、美佳さんが父から受け取ったのは結婚時の支度金200万円のみ。毎日4時頃に目が覚めて「なぜ父は私にだけ教えてくれなかったのだろう」と考え込み、夜も眠れない日が続きました。健太郎さんに話し合いを求めると「遺留分の話なら弁護士を通してくれ」と冷たく言われ、血の繋がった兄弟なのにお金の話になるとここまで関係がギクシャクするものかと悲しくなりました。認知症が進行する母の介護負担は今後さらに重くなることが予想される中、経済的にも精神的にも追い詰められた状況でした。
相談所からのご提案・解決までの流れ
まず、美佳さんの心理的負担を軽減するため、生前贈与と相続における権利について丁寧に説明しました。健太郎さんが受けた1,800万円は「特別受益」に該当し、相続時には遺産の前渡しとして扱われること、美佳さんには遺留分として法定相続分の2分の1の権利があることを確認しました。
次に、遺産の詳細調査を実施。自宅不動産の適正評価を行い、預貯金や生命保険なども含めた総遺産額を算定しました。その結果、特別受益を考慮した場合の美佳さんの遺留分は約1,100万円となることが判明しました。
健太郎さんとの交渉では、まず調停を申し立てました。調停では中立的な立場の調停委員が間に入り、感情的にならずに話し合いを進めることができました。美佳さんの介護負担についても考慮され、最終的に健太郎さんから遺留分相当額の支払いと、今後の母の介護費用の一部負担について合意が成立しました。
相談者の声

最初は家族関係が完全に壊れてしまうのではないかと不安でした。でも、専門家の方に法律的な権利をきちんと説明していただき、感情論ではなく客観的な事実に基づいて話し合いができるようになりました。調停を通じて兄との関係も少しずつ修復され、母の介護についても協力体制を築けるようになりました。何より、父が私をどう思っていたかという疑問も、生前の状況を整理する中で理解できるようになりました。一人で悩んでいた時間がもったいなかったと思います。銀行員として相続の知識はあったつもりでしたが、自分の家族のこととなると冷静に判断できないものですね。
担当者のコメント
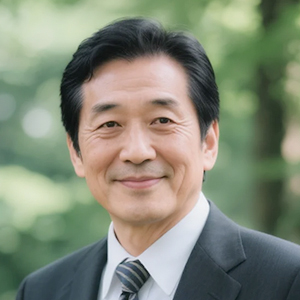
美佳さんのように、家族の介護を一手に引き受けながら経済的な不平等に悩まれる方は少なくありません。特別受益や遺留分といった法律的な権利は複雑で、感情的な対立も絡みやすい問題です。今回のケースでは、まず美佳さんの心理的な負担を理解し、法律的な権利を整理した上で、家族関係の修復も視野に入れた解決策を提案しました。調停という公的な制度を活用することで、感情的にならずに客観的な話し合いができ、結果として双方が納得できる解決に至りました。相続問題は早期の相談が重要です。一人で抱え込まずに、専門家にご相談いただければと思います。
