相談者様のプロフィール
吉田雅子さん(仮)、48歳、千葉県市川市在住。
公立中学校教諭として25年勤務、年収520万円。夫(50歳・会計事務所職員)、長男(22歳・大学生)、次男(19歳・専門学校生)の4人家族。
母(75歳・要介護3)は老人ホーム入所中。長兄(52歳・群馬県在住・製造業管理職)、次兄(50歳・埼玉県在住・自営業)との3人兄弟。
実家は千葉県船橋市内の築45年木造2階建て、土地評価額2,200万円。
ご相談の内容
2年前に父が急性心筋梗塞で他界し、遺産は実家不動産のみとなりました。父の死後、母の認知症が急激に進行し、老人ホームへの入所が必要となり、月額25万円の費用を兄弟3人で分担している状況でした。
当初、長兄の進さんは「実家を売却して現金で分割しよう」と提案しましたが、次兄の悟さんは「思い出の詰まった家を手放したくない。自分が買い取る」と反対。雅子さんも実家への愛着があり、売却に躊躇していました。しかし悟さんは「もう少し時間をくれ」と言いながら、自営業の収入が不安定で銀行融資が通らず、具体的な資金調達の目処が立たない状態が1年以上続きました。
進さんが痺れを切らして「もう勝手に売却手続きを進める」と宣言すると、悟さんが激怒して兄弟間で大喧嘩に。それ以来3人で顔を合わせることもなくなり、母の面会時も時間をずらすほど関係が悪化しました。雅子さんは連絡役として板挟みになり、夜中に目が覚めて「なぜ私だけがこんな思いを」と涙することも。実家は空き家となって荒れ放題で、近所からの苦情も寄せられるようになりました。
相談所からのご提案・解決までの流れ
まず、雅子さんの心理的負担を軽減するため、2年間の経緯を丁寧にお聞きし、兄弟それぞれの立場と想いを整理しました。実家への愛着と売却の必要性、どちらも理解できる状況であることを確認し、家庭裁判所の遺産分割調停を提案しました。
調停では、中立的な調停委員が間に入ることで感情的にならずに話し合いができます。まず不動産の適正評価を実施し、現在の市場価値を客観的に把握しました。また、母の今後の介護費用見込みも算出し、現実的な資金需要を明確にしました。
調停の場で、悟さんの実家への想いを尊重しつつ、現実的な資金調達が困難であることを冷静に話し合いました。最終的に、実家を売却して3等分する代わりに、売却前に思い出の品を整理する時間を十分確保し、近所への挨拶回りも3人で行うことで合意しました。売却益の一部を母の介護費用専用口座に預け、残りを3等分することで、全員が納得できる解決となりました。
相談者の声

2年間も膠着状態が続いて、兄弟関係が修復不可能になるのではないかと本当に心配でした。調停と聞くと大げさに感じましたが、実際は調停委員の方が温かく話を聞いてくださり、それぞれの立場を理解した上で現実的な解決策を一緒に考えてくださいました。次兄の実家への想いも無駄ではなく、売却前にゆっくり思い出を整理する時間をもらえたことで、家族みんなが納得して手放すことができました。今では兄弟3人で母の面会に行くこともでき、介護についても協力し合える関係に戻りました。一人で抱え込んでいた時間がもったいなかったです。
担当者のコメント
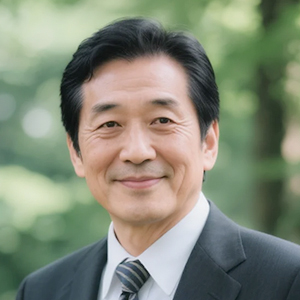
不動産の共有は感情的な対立を生みやすく、時間が経つほど関係が悪化する傾向があります。雅子さんのケースでは、それぞれが実家に対する想いを持ちながらも、現実的な解決が必要な状況でした。調停という公的制度を活用することで、感情論ではなく客観的な事実に基づいた話し合いができ、全員が納得できる解決に至りました。空き家の管理問題や近隣への迷惑なども考慮し、早期解決の重要性をご理解いただけました。不動産の共有問題は放置するほど複雑化します。感情的な対立が生じる前に、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
