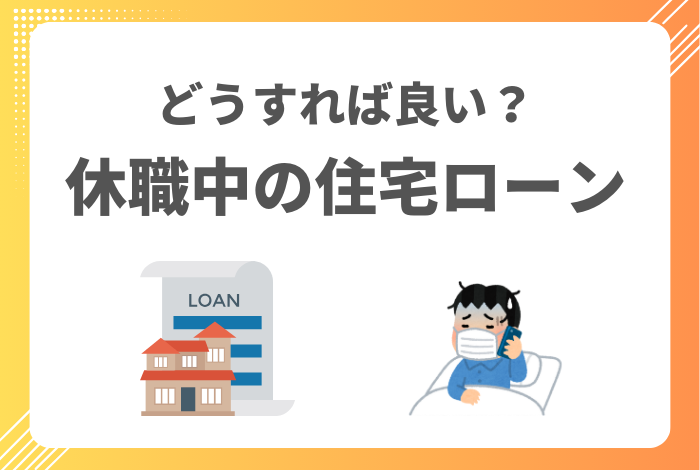
病気やケガで休職することになり、収入が減って住宅ローンの返済が厳しい…。「このままでは家を失ってしまうかもしれない」と、一人で不安を抱えていませんか?ご安心ください。休職中に住宅ローンの返済が困難になった場合でも、利用できる制度や正しい対処法があります。
大切なのは、決して一人で抱え込まず、適切な場所に適切なタイミングで相談することです。実際に、多くの方が早期の相談によって住宅を手放すことなく問題を解決されています。
この記事では、休職中の住宅ローン問題に直面したときに、まず何をすべきか、どんな選択肢があるのか、そして誰に相談すればよいのかを、時系列に沿って分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの不安が和らぎ、次の一歩を踏み出すための道筋が見えてくるはずです。
休職中の住宅ローン、放置は絶対NG!まず知っておきたい2つの基本

住宅ローンの問題は時間が経つほど選択肢が狭まります。まずは現実を正しく理解し、早期の対応がいかに重要かを把握しましょう。適切な知識があれば、冷静に対処することができます。
原則として返済義務はなくならない
休職という事情があっても、住宅ローンの返済は自動的に停止されることはありません。契約上の返済義務は継続し、返済が1日でも遅れると年14.6%程度の遅延損害金が発生するケースが一般的です。
たとえば月10万円の返済を1ヶ月滞納した場合、約1,200円の遅延損害金が上乗せされます。この金額は滞納期間が長引くほど膨らんでいくため、早期の対応が経済的負担を最小限に抑える鍵となります。まずはこの現実をしっかりと受け止めることから始めましょう。
滞納を続けるとどうなる?差し押さえ・競売までの流れ
返済の滞納が続くと、以下のような段階を経て最終的に自宅を失うリスクがあります。
滞納開始から3ヶ月程度で金融機関から催告書が届き、6ヶ月程度で期限の利益を喪失(残債の一括返済を求められる状態)します。その後、保証会社による代位弁済が行われ、最終的には裁判所による競売手続きが開始されるのが一般的な流れです。
競売では市場価格の7割程度での売却となることが多く、売却後も残債が残る可能性が高くなります。しかし、この段階に至る前に適切な対処をすれば、多くの場合で住宅を守ることは可能です。
【最初の1ヶ月】すぐにやるべきことリスト

休職が決まったら、まずは1ヶ月以内に以下の3つのステップを実行しましょう。この初期対応が、その後の選択肢の幅を大きく左右します。慌てずに一つずつ着実に進めることが重要です。
ステップ1:家計の収支を正確に把握する
最初に行うべきは、休職中の家計状況の正確な把握です。収入面では、傷病手当金や有給消化による給与、配偶者の収入などをすべて洗い出しましょう。
支出面では、住宅ローンだけでなく生活費、保険料、税金、その他のローンなど月々の固定費を詳細に書き出します。その上で、毎月いくら不足するのか、この状況がいつまで続く見込みかを明確にしてください。この数字が今後の対策を立てる際の基準となります。
家計簿アプリや表計算ソフトを活用すると、収支の管理がより正確で継続しやすくなります。
ステップ2:傷病手当金など、利用できる公的制度を確認・申請する
健康保険から支給される傷病手当金は、休職中の重要な収入源です。支給額は標準報酬日額の3分の2で、最長1年6ヶ月まで受給可能です。
申請には医師の意見書が必要なため、主治医との相談も欠かせません。また、業務上の病気やケガの場合は労災保険の休業補償給付の対象となり、こちらは給与の約8割が支給されます。症状によっては障害年金の受給資格もあるかもしれません。
これらの制度は申請しなければ受給できないため、勤務先の人事担当者や加入している健康保険組合に早急に確認し、必要な手続きを開始しましょう。
ステップ3:住宅ローンを借りている金融機関に電話相談する
最も重要なアクションが、金融機関への早期相談です。「返済が厳しくなりそうだ」と正直に伝えることで、金融機関側も対応策を検討してくれる可能性が高まります。
相談の際は、休職の理由、期間の見通し、現在の収支状況、利用できる公的制度などを整理して伝えましょう。また、返済継続への意思があることを明確に示すことも大切です。多くの金融機関では、顧客の状況に応じた相談窓口を設けており、様々な解決策を提案してもらえるケースが少なくありません。
電話での相談内容は記録を残し、担当者の名前も控えておくことをお勧めします。
金融機関との交渉で検討できる、具体的な返済負担の軽減策

金融機関では、顧客の状況に応じて様々な返済条件の変更に応じてくれる場合があります。以下の選択肢について、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で検討しましょう。
返済額を一時的に減額する(元金据え置き)
元金据え置きは、一定期間(通常6ヶ月〜2年程度)利息のみの支払いに変更する方法です。たとえば月々12万円の返済のうち利息が3万円の場合、この期間中は3万円のみの支払いとなります。
月々の負担は大幅に軽減されますが、据え置き期間中も利息は発生し続けるため、最終的な返済総額は増加します。また、据え置き期間終了後は通常の返済に戻るため、収入回復の見通しが立っていることが前提条件となるでしょう。
短期的な収入減少に対する有効な対策ですが、長期的な視点での検討が必要です。
返済期間を延長する(リスケジュール)
返済期間を延長することで、月々の返済額を恒久的に減らす方法です。たとえば残り20年のローンを25年に延長することで、月々の返済額を2〜3万円程度減らせるケースもあります。
この方法のメリットは、返済負担の軽減が恒久的に続くことです。一方、返済期間が延びる分、利息の総額は増加し、完済時の年齢も上がります。定年退職後も返済が続く可能性がある場合は、将来の収入計画もあわせて検討する必要があります。
金融機関によっては年齢制限がある場合もあるため、早めの相談が重要です。
団体信用生命保険(団信)の保障内容を確認する
住宅ローン契約時に加入した団体信用生命保険に、疾病保障特約が付帯されているケースがあります。がんと診断された場合や、脳卒中・急性心筋梗塞で所定の状態になった場合にローン残高が保険で完済される仕組みです。
最近では、うつ病などの精神疾患やすべての病気・ケガによる就業不能状態をカバーする商品も増えています。保障の適用条件は商品によって異なるため、保険証券や契約書類を確認し、必要に応じて保険会社に問い合わせましょう。
もし保障の対象となる場合は、医師の診断書などの必要書類を準備して速やかに請求手続きを行うことが大切です。
どうしても返済が困難な場合の最終手段

金融機関との交渉や公的制度の活用でも返済継続が困難な場合、以下の方法を検討する必要があります。いずれも重大な決断となるため、専門家への相談を強くお勧めします。
「任意売却」で自宅を売却し、残債を整理する
任意売却は、住宅ローンの残債がある状態で金融機関の合意を得て自宅を売却する方法です。市場価格での売却が可能なため、競売と比較して高値での売却が期待できます。
競売では市場価格の7割程度での売却となることが多いのに対し、任意売却では市場価格の8〜9割での売却が一般的です。また、売却時期や条件についてもある程度の調整が可能で、引っ越し費用の一部を売却代金から捻出できるケースもあります。
ただし、売却後に残債が残る場合は引き続き返済義務が生じること、信用情報に影響が出ることなどのデメリットも理解しておく必要があります。任意売却を成功させるには、不動産会社や金融機関との綿密な調整が不可欠です。
法律専門家への相談も視野に(債務整理)
住宅ローン以外にも複数の借入がある場合や、収入の回復見込みが立たない場合は、債務整理も選択肢の一つとなります。
個人再生であれば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額しつつ、住宅を維持できる可能性があります。ただし、安定した収入があることが条件となるため、休職中の申立ては慎重な検討が必要です。自己破産の場合は住宅を失うことになりますが、すべての債務から解放されます。
債務整理は人生の再スタートを切るための法的な手続きですが、その後の生活に大きな影響を与えるため、弁護士や司法書士といった専門家との十分な相談が欠かせません。
今からできる!将来のための備えと復職後の注意点

休職中の住宅ローン問題を解決した後も、同様の事態に備える準備と、復職後の安定した返済継続のための計画が重要です。一度経験した不安を繰り返さないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
就業不能保険や所得補償保険への加入を検討する
民間の就業不能保険や所得補償保険は、病気やケガで働けなくなった際の収入減少をカバーする保険です。傷病手当金が給与の約3分の2であるのに対し、これらの保険では給与の5〜7割程度を補償する商品が一般的です。
就業不能保険は長期間の就業不能状態をカバーし、所得補償保険は比較的短期間の収入減少に対応します。保険料は年齢や職業、補償額によって異なりますが、月額数千円から1万円程度で加入できるケースが多いでしょう。
ただし、既往症がある場合は加入が制限される可能性があるため、健康なうちに検討することが大切です。また、住宅ローンの返済額に見合った補償額を設定し、家計に無理のない保険料での加入を心がけましょう。
復職後に改めて返済計画を見直そう
復職できたからといって、すぐに以前と同じ生活水準に戻すのは危険です。時短勤務や配置転換により収入が減少している可能性や、治療費などの新たな支出が発生している場合もあります。
まずは復職後3〜6ヶ月程度の収支を記録し、安定した家計状況を把握しましょう。その上で、休職中に変更した返済条件を元に戻すか継続するかを慎重に判断してください。無理な返済計画は再び同じ問題を引き起こすリスクがあります。
また、緊急時の資金として生活費の3〜6ヶ月分の貯蓄を目標に、計画的な資産形成も再開しましょう。今回の経験を活かし、より安心できる家計管理体制を構築することが重要です。
【まとめ】休職中の住宅ローンが払えないときの対策
休職中の住宅ローン問題は、適切な対処により必ず解決の道が見つかります。以下のポイントを参考に、早めの行動を心がけてください。
- 早期対応が鍵:滞納が始まる前に金融機関に相談する
- 公的制度を活用:傷病手当金などの申請を速やかに行う
- 家計状況の正確な把握:収支を詳細に分析し、不足額を明確にする
- 返済条件の変更を相談:元金据え置きやリスケジュールなどの選択肢を検討
- 団信保障の確認:疾病保障特約の適用可能性をチェック
- 任意売却も選択肢:競売より有利な条件での売却を検討
- 専門家への相談:状況に応じて適切な専門家のサポートを受ける
- 将来への備え:就業不能保険への加入や復職後の返済計画見直し
休職という困難な状況で、住宅ローンの不安まで抱えるのは非常につらいことです。しかし、多くの方が同様の問題を乗り越えており、解決策は必ず存在します。
大切なのは一人で抱え込まず、適切なタイミングで適切な相談先に助けを求めることです。この記事で紹介した対処法と相談先を参考に、まずは第一歩を踏み出してください。あなたの勇気ある行動が、安心できる生活への道筋を作ります。

