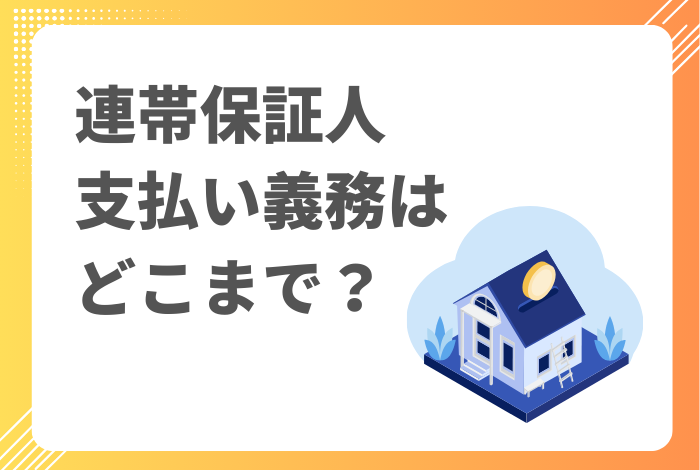
ある日突然、債権者から「連帯保証人として支払ってください」という請求が届いたとき、多くの方が「なぜ自分が?」「支払いを拒否できないの?」と困惑されるでしょう。
連帯保証人の責任は想像以上に重く、原則として支払い義務を拒否することはできません。しかし、すべてのケースで絶対に支払わなければならないわけではなく、状況によっては義務を免れたり減額できたりする場合もあります。
この記事では、連帯保証人の支払い義務の範囲や拒否できる例外的なケース、実際に請求が来た際の対処法について、法的な観点から詳しく解説します。
【大前提】連帯保証人の支払い義務は原則拒否できない

連帯保証人として契約を結んだ以上、主債務者が返済できなくなった場合の支払い義務を拒否することは原則としてできません。
これは法律で明確に定められており、「知らなかった」「そんなつもりはなかった」という理由では通用しないのが現実です。
なぜここまで厳格なのでしょうか。それは連帯保証人が「主債務者と同等の責任」を負う立場だからです。債権者からすれば、お金を貸した相手が返済できなくなったとき、連帯保証人がいることで確実に回収できるという安心感があります。
ただし、すべてのケースで絶対に支払わなければならないわけではありません。契約の経緯や状況によっては、支払い義務を免れたり減額したりできる場合もあるため、まずは冷静に状況を整理することが重要です。
なぜ拒否できない?「保証人」との決定的な違い
多くの方が混同しがちですが、「連帯保証人」と単なる「保証人」では、責任の重さが大きく異なります。連帯保証人は主債務者とほぼ同じ立場に置かれるため、債権者から請求されたら即座に支払わなければならないのです。
一方、通常の保証人には「まずは主債務者に請求してください」と言える権利があります。
また、保証人が複数いる場合は、借金を人数で割った金額だけ支払えばよいという決まりもあります。
比較表で一目瞭然!「連帯保証人」と「保証人」の違い
| 項目 | 連帯保証人 | 保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | なし | あり |
| 検索の抗弁権 | なし | あり |
| 分別の利益 | なし | あり |
| 責任の重さ | 主債務者と同等 | 補充的 |
連帯保証人に認められない3つの権利
連帯保証人には、通常の保証人が持つ3つの重要な権利が認められていません。
催告の抗弁権とは、債権者に対して「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利です。
検索の抗弁権は、「主債務者に財産があるなら、そちらから先に回収してください」と求める権利。
分別の利益は、保証人が複数いる場合に、借金を人数で割った分だけ支払えばよいという権利です。
これらの権利がすべて認められていないため、連帯保証人は債権者から請求されたら、主債務者の状況に関係なく、借金の全額を支払う義務を負います。
【2020年民法改正】知っておきたい連帯保証人の新ルール
2020年4月に施行された改正民法により、連帯保証人の保護を強化する新しいルールが導入されました。これらの変更点を理解しておくことで、より適切な対応ができるようになります。
特に重要なのは、個人が事業用融資の連帯保証人になる際の規制強化です。過度な責任を負わせないための仕組みが整備され、連帯保証人の立場がより明確になりました。
契約時に上限額(極度額)の設定が必須に
改正民法では、個人が事業用融資の連帯保証人になる場合、必ず「極度額」という上限金額を設定することが義務付けられました。この金額を超えて責任を負うことはありません。
極度額が設定されていない契約は無効となるため、2020年4月以降に結んだ契約で極度額の記載がない場合は、契約自体が成立していない可能性があります。契約書を確認し、極度額の記載がない場合は専門家に相談しましょう。
情報提供義務について
改正民法では、債権者が連帯保証人に対して、主債務者の返済状況や債務の履行状況について情報提供する義務も新たに規定されました。連帯保証人は債権者に対して、主債務者がどのような状況にあるかを問い合わせることができます。
この情報を基に、適切な対応を検討することが可能になったため、請求を受けた際は必ず債権者に詳しい状況を確認することをお勧めします。
連帯保証人の支払い義務はどこまで?責任を負う範囲

連帯保証人として責任を負う範囲は、元金だけではありません。利息、遅延損害金、そして債権回収にかかった費用まで含まれる場合があります。そのため、実際の支払い額は借入当初の金額を大幅に上回ることも珍しくありません。
ただし、2020年の民法改正により、個人が事業用融資の連帯保証人になる場合は「極度額」という上限が設定されるようになりました。この上限を超えて責任を負うことはないため、まずは契約書を確認して極度額の記載があるかどうかを確認しましょう。
主債務者と全く同じ支払い義務(元金・利息・遅延損害金など)
連帯保証人は主債務者と同等の責任を負うため、元金だけでなく、契約で定められたすべての債務について支払い義務があります。これには利息、遅延損害金、そして場合によっては債権回収にかかった費用も含まれます。
例えば、100万円の借金で年利15%、遅延損害金が年利20%の契約の場合、返済が1年間滞ると、元金100万円に加えて遅延損害金20万円、合計120万円の支払い義務が発生します。
さらに、債権者が弁護士に依頼して回収を行った場合の弁護士費用や、裁判費用なども連帯保証人の負担となる可能性があります。このように、実際の支払い額は当初の借入金額を大幅に上回ることがあるため、早期の対応が重要です。
契約で定められた上限額(極度額)の範囲内
2020年4月以降に締結された個人の事業用融資に関する連帯保証契約では、必ず「極度額」という上限金額が設定されています。この金額を超えて責任を負うことはありません。
極度額は契約書に明記されており、この金額が連帯保証人の責任の上限となります。例えば、極度額が500万円と設定されている場合、借金の総額が800万円になったとしても、連帯保証人の責任は500万円までとなります。
ただし、極度額が設定されていない古い契約や、個人の事業用融資以外の契約では、この制限は適用されません。自分の契約がどちらに該当するかを確認し、極度額の有無を必ず確認しましょう。
それでも連帯保証人が支払い義務を免れる・減額できる5つのケース

連帯保証人の支払い義務は原則として拒否できませんが、例外的に義務を免れたり減額したりできる場合があります。これらのケースに該当する可能性がある場合は、諦めずに専門家に相談することが重要です。
以下の5つのケースは、実際の判例や法的根拠に基づいて義務を免れる可能性があるものです。ただし、判断は複雑で専門的な知識が必要となるため、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
ケース1:保証契約そのものが無効・取り消しになる場合
連帯保証契約自体に問題がある場合、契約が無効または取り消しとなり、支払い義務を免れることができます。最も多いのは、署名や捺印を偽造されたケースや、詐欺や脅迫によって契約させられたケースです。
また、契約時に十分な説明を受けていなかった場合や、認知症などで判断能力が不十分だった場合も、契約の取り消しが認められる可能性があります。特に高齢者の場合は、契約時の判断能力について慎重に検討する必要があります。
さらに、2020年4月以降の個人事業用融資では、極度額の設定が義務付けられているため、極度額が設定されていない契約は無効となります。契約書を確認し、これらの要件を満たしていない場合は、専門家に相談して契約の有効性を検討しましょう。
ケース2:借金が「時効」を迎えている場合(時効の援用)
借金には時効があり、一定期間が経過すると支払い義務が消滅します。連帯保証人の場合も同様で、最後の返済や請求から5年(商事債権の場合)または10年(一般の債権の場合)が経過すると、時効により支払い義務を免れることができます。
ただし、時効は自動的に成立するものではなく、「時効の援用」という手続きを行う必要があります。また、途中で支払いを行ったり、債務を承認したりすると、時効期間がリセットされてしまうため注意が必要です。
時効の判断は複雑で、請求書の送付や裁判の提起などにより時効が中断されている場合もあります。時効の可能性がある場合は、安易に支払いの約束をせず、まずは専門家に相談して時効の成立可能性を確認しましょう。
ケース3:連帯保証人自身が「債務整理」をする場合
連帯保証人自身が経済的に困窮している場合、債務整理を行うことで支払い義務を減額または免除してもらうことができます。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
任意整理では、債権者と直接交渉して支払い条件を変更してもらいます。個人再生では、裁判所の手続きにより債務を大幅に減額できる場合があります。自己破産では、すべての債務が免除されますが、一定の財産を失うことになります。
どの方法が適しているかは、連帯保証人の収入や財産、他の借金の状況などにより異なります。また、債務整理を行うと信用情報に記録されるため、将来のローンやクレジットカードの利用に影響が出る可能性があります。
ケース4:主債務者が借金を完済した場合
主債務者が借金を完済すれば、連帯保証人の支払い義務も当然に消滅します。ただし、完済したにも関わらず連帯保証人に請求が来る場合は、債権者が完済の事実を把握していない可能性があります。
このような場合は、主債務者から完済証明書や返済完了通知書を取得し、債権者に提示することで請求を停止させることができます。また、主債務者が一部返済を行った場合は、その分だけ連帯保証人の責任も減額されます。
主債務者の返済状況については、債権者に対して情報開示を求めることができます。請求を受けた際は、必ず現在の債務残高と主債務者の返済状況を確認し、適切な対応を検討しましょう。
ケース5:債権者との交渉で減額や分割払いに応じてもらえた場合
債権者との交渉により、支払い金額の減額や分割払いに応じてもらえる場合があります。特に、連帯保証人に十分な支払い能力がない場合や、長期間にわたって債権が回収できずにいる場合は、債権者も現実的な回収を検討することがあります。
交渉を行う際は、連帯保証人の収入や財産状況を正確に把握し、現実的な返済計画を提示することが重要です。また、一括返済が困難な場合は、分割払いの条件や期間についても具体的に提案しましょう。
ただし、交渉は専門的な知識と経験が必要であり、不適切な対応をすると状況が悪化する可能性もあります。債権者との交渉を行う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
ある日突然、請求が…!連帯保証人が今すぐ取るべき4ステップ

連帯保証人として請求を受けた際は、パニックになりがちですが、冷静な対応が問題解決の鍵となります。適切な手順を踏むことで、最善の解決策を見つけることができるでしょう。
以下の4つのステップは、請求を受けた際の基本的な対応方法です。特に重要なのは、安易に支払いの約束をしないことです。少額でも支払いを行うと、時効が中断したり、債務を承認したことになったりする可能性があります。
STEP1:まずは落ち着いて請求内容を精査する
請求書を受け取ったら、まずは内容を詳しく確認しましょう。元金、利息、遅延損害金の内訳、請求の根拠となる契約書の内容、そして請求者が正当な債権者であるかどうかを確認します。
特に注意すべきは、請求金額の計算が正しいかどうかです。利息や遅延損害金の計算方法、起算日、適用される利率などを契約書と照らし合わせて確認しましょう。また、債権が第三者に譲渡されている場合は、譲渡の事実と譲渡通知の有無も確認が必要です。
契約書が手元にない場合は、債権者に対して契約書の写しの提供を求めることができます。また、個人情報開示請求により、債権者が保有する契約関係の書類を確認することも可能です。
STEP2:主債務者の状況を確認する
請求を受けたら、主債務者の現在の状況を確認しましょう。返済の意思があるか、返済能力はどの程度あるか、他の債務はないかなどを聞き取り、総合的に判断することが重要です。
主債務者が返済の意思を示している場合は、債権者との交渉において有利に働く可能性があります。一方、主債務者が行方不明になっている場合や、返済を完全に放棄している場合は、連帯保証人としての責任を重く考える必要があります。
また、主債務者が既に債務整理を行っている場合や、自己破産を検討している場合は、その影響を考慮して対応策を検討しましょう。主債務者の状況によって、最適な解決方法は変わってきます。
STEP3:【重要】安易に支払いの約束をしない
請求を受けても、すぐに支払いの約束をしてはいけません。たとえ少額であっても、支払いを行うと債務を承認したことになり、時効が中断される可能性があります。
また、「とりあえず一部だけ支払う」という対応も危険です。一部でも支払いを行うと、残りの債務についても支払い義務があることを認めたことになってしまいます。さらに、支払いを行った日から新たに時効期間が開始されるため、時効の援用ができなくなる可能性があります。
債権者から「今すぐ支払わないと法的措置を取る」などと迫られても、慌てて対応する必要はありません。まずは専門家に相談し、適切な対応方法を検討してから行動しましょう。
STEP4:速やかに専門家(弁護士・司法書士)へ相談する
連帯保証人の問題は法的に複雑で、一般の方が適切に対応することは困難です。請求を受けたら、できるだけ早く弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
専門家に相談することで、契約の有効性、時効の可能性、債務整理の選択肢、債権者との交渉方法など、様々な角度から検討してもらうことができます。また、専門家が代理人として債権者と交渉することで、より有利な条件で解決できる可能性もあります。
相談の際は、契約書、請求書、これまでの経緯を示す書類などを持参しましょう。正確な情報を提供することで、より適切なアドバイスを受けることができます。
連帯保証人の支払い義務に関するよくある質問(Q&A)

連帯保証人の支払い義務について、多くの方が抱く疑問をQ&A形式でまとめました。これらの質問は実際の相談現場でよく寄せられるもので、具体的な状況に応じた対応方法を知ることで、適切な判断ができるようになります。
Q. 主債務者が自己破産したら、支払い義務はどうなりますか?
主債務者が自己破産手続きを行い、免責許可を受けたとしても、連帯保証人の支払い義務は消滅しません。連帯保証人は主債務者とは別の独立した債務者として扱われるため、主債務者の自己破産の影響を受けないのです。
つまり、主債務者が自己破産によって借金を帳消しにしても、債権者は連帯保証人に対して全額の支払いを請求することができます。この場合、連帯保証人は主債務者に代わって債務を履行する義務を負うことになります。
ただし、連帯保証人自身も支払いが困難な場合は、連帯保証人も債務整理を検討することができます。主債務者の自己破産後に連帯保証人が支払いを行った場合は、主債務者に対して求償権を行使することができますが、自己破産した主債務者から回収することは現実的には困難です。
Q. 離婚した元配偶者の連帯保証人になっている場合、支払い義務は残りますか?
離婚したとしても、連帯保証人としての支払い義務は消滅しません。連帯保証契約は夫婦関係とは独立した契約であるため、離婚によって自動的に解除されることはないのです。
例えば、夫の事業資金の借入について妻が連帯保証人になっていた場合、離婚後も妻は連帯保証人としての責任を負い続けます。借金の返済が滞れば、債権者は元妻に対して支払いを請求することができます。
このような状況を避けるためには、離婚時に連帯保証人の地位から外れるための手続きを行う必要があります。債権者の同意を得て連帯保証契約を解除するか、他の保証人に変更してもらうなどの対応が必要です。ただし、債権者がこれらの変更に応じる義務はないため、交渉は困難になる場合があります。
Q. 親が亡くなり、連帯保証人の地位を相続してしまいました。どうすればいいですか?
連帯保証人の地位は相続財産に含まれるため、相続人が相続放棄を行わない限り、連帯保証人としての責任を引き継ぐことになります。ただし、相続放棄を行えば、この責任を免れることができます。
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間内に手続きを行えば、連帯保証人の地位を含むすべての相続財産を放棄することができます。
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も含めてすべての相続財産を放棄することになります。また、すでに相続財産の一部を処分したり、債務の一部を支払ったりしている場合は、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を検討する場合は、早めに専門家に相談することが重要です。
Q. 支払った分は、主債務者に請求できますか?(求償権について)
連帯保証人が債務を支払った場合、主債務者に対して「求償権」を行使し、支払った金額を請求することができます。これは法律で認められた権利で、連帯保証人が不当に損失を被ることを防ぐためのものです。
求償権には、支払った元金だけでなく、利息や遅延損害金、さらには支払いのために要した費用(弁護士費用など)も含まれます。また、求償権にも利息を付けることができるため、主債務者の返済が遅れるほど、請求できる金額は増加します。
ただし、求償権があっても、主債務者に支払い能力がなければ回収は困難です。特に、主債務者が自己破産している場合や、行方不明になっている場合は、実際に回収できる可能性は低いでしょう。そのため、連帯保証人になる際は、将来的に自分が全額を負担することになる可能性も考慮しておく必要があります。
まとめ:連帯保証人の支払い義務で悩んだら、一人で抱え込まず専門家へ
連帯保証人の支払い義務は原則として拒否できませんが、契約の有効性、時効の可能性、債務整理の選択肢など、様々な角度から検討することで解決の糸口が見つかる場合があります。
重要なのは、請求を受けても慌てて対応せず、まずは冷静に状況を整理することです。安易に支払いの約束をしたり、少額でも支払いを行ったりすると、時効が中断されたり、債務を承認したことになったりする可能性があります。
連帯保証人の問題は法的に複雑で、一般の方が適切に対応することは困難です。請求を受けたら、できるだけ早く弁護士や司法書士などの専門家に相談し、最適な解決方法を見つけることをお勧めします。
一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、適切な対応を行うことが問題解決への近道となるでしょう。

