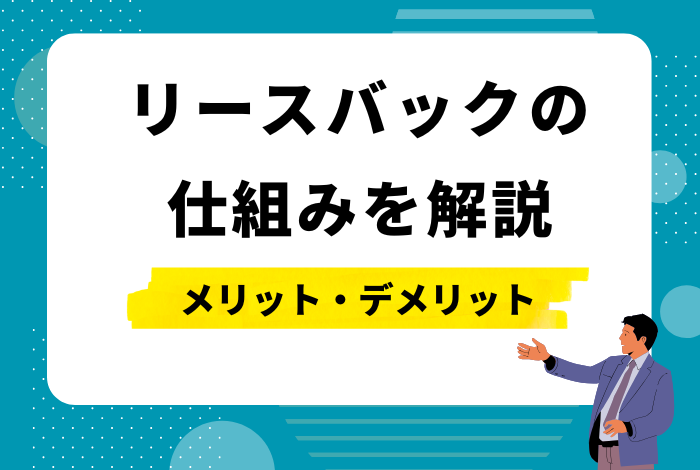
自宅を手放すことなく、まとまった資金を手に入れられる「リースバック」。高齢化社会の進展や経済環境の変化により、近年注目を集めている資金調達方法です。
住み慣れた我が家を離れることなく現金が手に入る一方で、所有権を失うことや家賃負担が発生するなど、慎重に検討すべき側面も存在します。
この記事では、リースバックの基本的な仕組みから契約時の注意点まで、利用を検討されている方が知っておくべき情報を解説します。
リースバックとは?まずは基本の仕組みをわかりやすく解説

リースバックとは、自宅を売却して現金を受け取った後、その物件を賃貸として借り続けることができる仕組みです。売却と賃貸借契約を同時に行うため、住環境を変えることなく資金調達が可能となります。
従来の不動産売却では物件を手放す必要がありましたが、リースバックなら住み続けながら資金を確保できる点が大きな特徴です。老後資金の確保や債務整理、相続対策など、さまざまな目的で活用されています。
リースバックの基本的な仕組み【図解】
リースバックの流れは以下の通りです。
【Step1】売却契約
所有者が自宅をリースバック事業者に売却し、売却代金を受け取ります。この時点で物件の所有権は事業者に移転します。
【Step2】賃貸借契約
売却と同時に、事業者と賃貸借契約を締結。元所有者は賃借人として、毎月家賃を支払いながら同じ住まいに住み続けます。
【Step3】買戻しオプション
多くの場合、将来的に物件を買い戻すことができるオプションが用意されています。ただし、買戻し価格は売却時より高く設定されるのが一般的です。
この仕組みにより、住居の確保と資金調達を同時に実現できるのがリースバックの特徴といえます。
どんな人が利用している?具体的な活用ケースを紹介
リースバックは多様な目的で活用されています。最も多いケースは、60歳以上の高齢者が老後資金を確保するための利用です。年金だけでは生活費が不足する場合や、医療費・介護費用の準備として活用されています。
事業資金の調達でも頻繁に利用されます。自営業者や中小企業経営者が、事業の運転資金や設備投資資金を調達する際、銀行融資が困難な状況でもリースバックなら対応可能です。
また、相続対策としての活用も増えています。相続時に不動産を現金化しておくことで、相続税の納税資金を確保したり、複数の相続人間での分割を簡単にしたりできます。離婚時の財産分与や、住宅ローンの返済が困難になった場合の任意売却に代わる選択肢としても注目されています。
【5ステップで理解】リースバックの申し込みから契約までの流れ

リースバックの利用を決定してから実際に資金を受け取るまでの流れは、おおむね5つのステップに分けられます。全体的な期間は1〜2ヶ月程度が目安となりますが、物件の条件や事業者によって変動します。
各ステップで必要な書類や注意点を事前に把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。複数の事業者を比較検討する場合は、この流れを参考にして適切なタイミングで各社からの提案を受けることが大切です。
ステップ1:専門家への相談と物件の査定
まず、リースバック事業者に相談を行い、物件の査定を受けます。この段階では、物件の立地条件、築年数、間取り、周辺環境などを総合的に評価します。
査定では、登記簿謄本、固定資産税評価証明書、建物図面などの書類が必要になります。住宅ローンが残っている場合は、残債額も重要な判断材料となるため、返済予定表も準備しておきましょう。
事業者によっては、現地調査を行って物件の状況を詳しく確認します。この際、修繕が必要な箇所があれば、売却価格に影響する可能性があるため、事前に把握しておくことが重要です。査定結果は通常1週間程度で提示されます。
ステップ2:売買価格と賃料の提示・条件交渉
査定結果を基に、売買価格と月々の家賃(リース料)が提示されます。この段階で、買戻しに関する条件も同時に説明を受けます。
売買価格は一般的に市場価格の7〜8割程度となることが多く、家賃は売却価格に対して年利8〜13%程度で設定されるのが相場です。ただし、物件の条件や事業者によって大きく異なるため、複数社から提案を受けることをお勧めします。
条件に納得がいかない場合は、この段階で交渉を行います。家賃の減額や買戻し期間の延長など、可能な範囲での調整を相談してみましょう。最終的な条件が固まったら、契約書の内容を詳しく確認し、不明点があれば必ず質問することが大切です。
ステップ3:売買契約と賃貸借契約の締結
条件に合意したら、売買契約書と賃貸借契約書を同日に締結します。この際、契約書の内容を十分に理解することが重要です。
売買契約書では、売却価格、決済日、所有権移転の条件などを確認します。賃貸借契約書では、家賃の金額、支払い時期、契約期間、更新条件、修繕費用の負担区分などを詳しく検討しましょう。
特に重要なのは、賃貸借契約が「普通借家契約」か「定期借家契約」かという点です。普通借家契約なら更新が可能ですが、定期借家契約では契約期間満了時に必ず退去する必要があります。将来的な住み続けられる期間に大きく影響するため、必ず確認してください。
ステップ4:売却代金の受け取りと所有権の移転
契約書に記載された決済日に、売却代金の受け取りと所有権の移転登記が行われます。住宅ローンが残っている場合は、売却代金から優先的に完済されます。
決済は通常、司法書士立会いのもと行われ、必要書類の確認や登記手続きが進められます。この日をもって、物件の所有権は正式に事業者に移転し、同時に賃貸借契約も開始となります。
売却代金から住宅ローンの残債、諸費用(登記費用、仲介手数料など)を差し引いた金額が手元に残ります。諸費用は売却価格の3〜5%程度が目安となるため、事前に計算しておくことが重要です。
ステップ5:家賃の支払い開始と住み替えの選択
所有権移転後、翌月分から家賃の支払いが開始されます。支払い方法は銀行振込が一般的で、毎月指定日までに事業者の口座に振り込みます。
家賃の支払いが滞った場合は、通常の賃貸借契約と同様に催促や契約解除の手続きが行われる可能性があります。長期的な支払い計画を立てて、無理のない範囲で契約することが大切です。
また、この時点で将来的な住み替えについても検討を始めることをお勧めします。買戻しを行う場合は、事前に資金計画を立てる必要があります。買戻しを行わない場合は、契約期間満了時の住み替え先を早めに探すことで、スムーズな移転が可能になります。
リースバックのメリット7選|住み続けながら資金を確保

リースバックを利用することで得られるメリットは多岐にわたります。単純な資金調達にとどまらず、税負担の軽減や相続対策、プライバシーの保護など、さまざまな側面で利用者にとって有益な効果をもたらします。
ここでは、リースバックならではの7つの主要なメリットを詳しく解説します。それぞれのメリットがどのような状況で特に有効なのかも併せて説明するため、ご自身の状況と照らし合わせながら検討してみてください。
【メリット1 】現在の住まいを手放さずに済む
最大のメリットは、愛着のある自宅に住み続けながら資金を確保できることです。長年住み慣れた環境を変える必要がなく、近所付き合いや生活パターンを維持できます。
特に高齢者の場合、住環境の変化は心身に大きな負担をもたらすことがあります。リースバックなら、慣れ親しんだ地域での生活を続けながら、老後資金を確保することが可能です。
子どもの学区を変えたくない場合や、介護が必要な家族がいる場合にも、住み慣れた環境を維持できる点は大きなメリットといえるでしょう。引っ越しに伴う費用や手間も不要となり、経済的・精神的な負担を軽減できます。
【メリット2】最短でまとまった現金が手に入る
リースバックは、他の資金調達方法と比較して短期間で現金を手に入れることができます。相談から資金受け取りまで、最短で1ヶ月程度で完了することも可能です。
銀行融資の場合、審査に時間がかかったり、担保や保証人が必要になったりしますが、リースバックは不動産を売却するため、比較的スムーズに手続きが進みます。
急な医療費や事業資金が必要な場合、借入れの審査が通りにくい高齢者の場合でも、物件に価値があればリースバックを利用できる可能性があります。現金化のスピードが重要な状況において、有効な選択肢となるでしょう。
【メリット3】資金の使い道に制限がない
リースバックで得た資金は、使い道に制限がありません。住宅ローンの返済や事業資金、老後資金、医療費、子どもの教育費など、どのような目的にも活用できます。
銀行融資の場合、資金使途が限定されることが多く、使い道を証明する書類の提出が求められます。しかし、リースバックは売却による収入のため、こうした制約がありません。
特に、複数の目的で資金が必要な場合や、将来的に資金需要が変化する可能性がある場合には、この柔軟性は大きなメリットとなります。計画的な資金運用が可能になり、長期的な資産管理に役立てることができます。
【メリット4】固定資産税などの維持費が不要になる
物件の所有権を手放すことで、固定資産税や都市計画税の支払い義務がなくなります。これらの税金は毎年継続的に発生するため、長期的には大きな負担軽減となります。
また、火災保険料や地震保険料の支払いも原則として大家(事業者)の負担となります。マンションの場合は管理費や修繕積立金も同様です。
ただし、賃貸借契約の内容によっては、一部の維持費用を借主が負担する場合もあります。契約時に費用負担の区分を明確にしておくことが重要です。これらの維持費が不要になることで、毎月の家計負担が軽減され、より計画的な資金運用が可能になります。
【メリット5】将来的に家を買い戻す選択肢がある
多くのリースバック契約では、将来的に物件を買い戻すオプションが設けられています。経済状況が改善したり、資金調達の目的が達成されたりした場合に、再び所有者になることができます。
買戻し価格は通常、売却価格より高く設定されますが、事前に条件が明確になっているため、計画的な資金準備が可能です。買戻し期間についても、契約時に定められるため、長期的な生活設計に組み込むことができます。
ただし、買戻しは権利であって義務ではないため、経済状況や生活環境の変化に応じて柔軟に判断できる点もメリットです。選択肢を残しながら、当面の資金需要に対応できる仕組みといえるでしょう。
【メリット6】ご近所に知られずに手続きを進められる
リースバックの手続きは、外見上は何も変わらないため、近所の人に知られることなく進められます。通常の不動産売却のように、売却看板が立てられたり、内覧希望者が頻繁に訪れたりすることがありません。
経済的な事情で資金調達が必要な場合でも、プライバシーを守りながら手続きを進めることができます。特に地域コミュニティとの関係を重視する場合や、子どもの学校関係への影響を避けたい場合には、この配慮は重要です。
手続きもシンプルで、事業者との間だけで完結するため、多くの関係者が関与する必要がありません。精神的な負担を軽減しながら、必要な資金を確保できる点は大きなメリットといえます。
【メリット7】不動産相続のトラブルを回避できる
不動産を現金化しておくことで、相続時のトラブルを回避できます。不動産は分割が困難で、相続人間での評価額に対する意見の相違が生じやすい財産です。
リースバックを利用して現金化しておけば、相続財産の分割が簡単になり、相続税の納税資金も確保できます。また、賃借権は相続されるため、残された家族が引き続き住み続けることも可能です。
特に、相続人が複数いる場合や、不動産以外の財産が少ない場合には、事前の現金化は有効な相続対策となります。家族間の関係を良好に保ちながら、円滑な相続手続きを実現できるでしょう。
契約前に必ず確認!リースバックのデメリットと5つのリスク

リースバックにはメリットがある一方で、契約前に十分理解しておくべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に把握することで、後悔のない判断ができるようになります。
特に、所有権の喪失や継続的な家賃負担は、長期的な生活設計に大きな影響を与える要素です。ここでは、リースバック契約において注意すべき5つの主要なデメリットとリスクを詳しく解説します。
【デメリット1】家の所有権を失う
リースバックでは、売却と同時に物件の所有権を完全に失います。これは単なる名義変更にとどまらず、財産としての不動産を手放すことを意味します。
所有権を失うことで、物件の改装や増築などは大家の許可が必要になります。ペットの飼育や楽器の演奏など、生活スタイルに制限が生じる可能性もあります。
また、将来的な不動産価格の上昇によるメリットを享受できません。長期的に見れば、不動産価値の上昇分を失うことになる可能性があります。所有者としての権利や自由度を重視する場合には、このデメリットは特に大きな影響を与えるでしょう。
【デメリット2】売却価格は市場価格より低くなる傾向
リースバックの売却価格は、通常の不動産売却の市場価格と比較して2〜3割程度低く設定されることが一般的です。これは、事業者が賃貸経営リスクを負うことや、買戻しオプションを提供することが影響しています。
市場価格が3000万円の物件であれば、リースバック価格は2100万円〜2400万円程度になる可能性があります。この価格差は、長期的に見れば大きな機会損失となり得ます。
ただし、通常の売却では仲介手数料や引っ越し費用などが発生するのに対し、リースバックではこれらの費用が不要となる場合が多いため、実質的な手取り額の差は縮小する場合もあります。総合的なコスト比較を行うことが重要です。
【デメリット3】毎月の家賃が発生する
所有者として住んでいた時期には不要だった家賃が、毎月発生するようになります。この家賃は、売却価格に対して年率8〜13%程度で設定されることが多く、周辺の賃貸相場より高めになる傾向があります。
例えば、2000万円で売却した場合、年間160万円〜260万円、月額にすると13万円〜22万円程度の家賃が発生します。この負担は契約期間中継続するため、長期的な家計への影響を慎重に検討する必要があります。
家賃の支払いが困難になった場合は、通常の賃貸借契約と同様に退去を求められる可能性があります。安定した収入の確保や、家賃負担能力の維持が重要な要素となるでしょう。
【デメリット4】買戻し価格は売却時より高くなる
買戻しオプションがある場合でも、買戻し価格は売却価格より高く設定されるのが一般的です。通常、売却価格の110%〜130%程度となることが多く、実質的に利息を支払うような形になります。
2000万円で売却した物件を買い戻す場合、2200万円〜2600万円程度の資金が必要になります。さらに、買戻し可能期間にも制限があるため、期間内に十分な資金を準備できない場合は、買戻しの機会を失うことになります。
買戻しを前提として契約する場合は、将来的な資金調達計画を慎重に立てることが重要です。計画通りに資金を確保できない場合のリスクも考慮に入れておく必要があります。
【デメリット5】契約形態次第では永住が保証されない
賃貸借契約の種類によっては、永続的に住み続けることが保証されない場合があります。特に「定期借家契約」の場合、契約期間満了時に必ず退去する必要があります。
定期借家契約では、たとえ家賃の支払いに問題がなくても、契約期間が終了すれば更新はできません。一方、「普通借家契約」であれば、正当な理由がない限り更新拒絶はできないため、より長期的な居住が可能です。
契約時に、どちらの契約形態が採用されるかを必ず確認しましょう。将来的な住み続けられる期間は、生活設計に大きく影響する重要な要素です。不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
あなたはどっち?リースバックが向いている人・向いていない人の特徴

リースバックは万能な解決策ではありません。利用者の状況や目的によって、最適な選択肢かどうかが大きく変わります。ここでは、リースバックの利用が推奨されるケースと、他の選択肢を検討した方が良いケースを具体的に解説します。
リースバックの利用をおすすめするケース
現在の住環境を維持しながら資金調達が必要な方に、リースバックは最適な選択肢となります。特に、60歳以上の高齢者で年金収入だけでは生活費が不足する場合、住み慣れた地域での生活を続けながら老後資金を確保できます。
急な医療費や介護費用が発生した際にも、迅速な資金調達が可能です。銀行融資が困難な状況でも、不動産に価値があればリースバックを利用できる可能性があります。
事業を営んでいる方で、運転資金や設備投資資金が必要な場合にも適しています。特に、店舗兼住宅として利用している物件の場合、事業の継続と住居の確保を同時に実現できます。
相続対策としても有効で、相続人が複数いる場合や、相続税の納税資金を事前に準備したい場合に活用できます。また、近所に知られずに手続きを進めたい方や、引っ越しに伴う負担を避けたい方にも適した選択肢です。
リースバック以外の選択肢を検討すべきケース
毎月の家賃負担が経済的に困難な場合は、リースバック以外の選択肢を検討することをお勧めします。年金収入や安定した収入源がない場合、家賃の支払いが困難になり、最終的に退去を余儀なくされる可能性があります。
住宅ローンの残債が物件価値を上回っている場合(オーバーローン)も、リースバックの利用は困難です。この場合は、任意売却や個人再生などの債務整理手続きを検討する必要があります。
できるだけ高い価格で物件を売却したい場合も、通常の不動産売却の方が適しています。リースバックは売却価格が市場価格より低くなる傾向があるため、売却益を最大化したい場合には不向きです。
将来的に買戻しを強く希望しているものの、買戻し資金の調達見込みが立たない場合も慎重な検討が必要です。買戻しができない場合のリスクを十分に理解し、受け入れられるかどうかを判断することが重要です。
【目的別】リースバックと他の資金調達手段との違いを徹底比較

自宅を活用した資金調達方法は、リースバック以外にも複数の選択肢があります。それぞれの仕組みや条件、メリット・デメリットを理解することで、最適な選択肢を見つけることができます。
ここでは、リースバックと主要な3つの資金調達方法を比較し、どのような状況でどの方法が適しているかを解説します。
「リバースモーゲージ」との違い
リバースモーゲージは、自宅を担保に融資を受け、契約者が亡くなった後に物件を売却して返済する仕組みです。リースバックとは異なり、物件の所有権は維持されます。
| 項目 | リースバック | リバースモーゲージ |
|---|---|---|
| 所有権 | 失う | 維持される |
| 資金調達方法 | 売却代金 | 融資 |
| 月々の負担 | 家賃 | 利息のみ |
| 年齢制限 | なし | 通常55歳以上 |
| 配偶者の保護 | 賃借権継承 | 継続居住可能 |
リバースモーゲージは、所有権を維持したい場合や、相続人に不動産を残したい場合に適しています。ただし、金利上昇リスクや物件価値下落リスクがあり、最終的な返済額が不透明になる可能性があります。
一方、リースバックは年齢制限がなく、確実に現金を受け取れる点がメリットです。また、家賃は固定されているため、月々の支払額が明確で生活設計がしやすくなります。
「通常の不動産売却」との違い
通常の不動産売却は、物件を第三者に売却して現金を受け取る方法です。リースバックと比較して、売却価格が高くなる傾向があります。
| 項目 | リースバック | 通常の不動産売却 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格の7-8割 | 市場価格 |
| 居住継続 | 可能 | 不可能 |
| 手続き期間 | 1-2ヶ月 | 3-6ヶ月 |
| 仲介手数料 | 不要な場合が多い | 売却価格の3% |
| 引っ越し費用 | 不要 | 必要 |
通常の売却は、売却価格を重視する場合や、住み替えを前提とする場合に適しています。特に、住宅ローンの完済や相続税の納税などで、まとまった資金が必要な場合には有効です。
リースバックは、住環境の維持を重視する場合や、迅速な資金調達が必要な場合に適しています。売却価格は低めでも、引っ越し費用や仲介手数料が不要となるため、実質的な手取り額の差は縮小する場合もあります。
「任意売却」との違い
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、競売を避けて自主的に物件を売却する方法です。債務整理の一環として行われることが多く、債権者の合意が必要です。
| 項目 | リースバック | 任意売却 |
|---|---|---|
| 利用目的 | 資金調達 | 債務整理 |
| 住宅ローン | 完済が前提 | 残債あり |
| 居住継続 | 可能 | 通常は不可能 |
| 信用情報 | 影響なし | 影響あり |
| 債権者の同意 | 不要 | 必要 |
任意売却は、住宅ローンの返済が困難で、競売による強制売却を避けたい場合に選択されます。ただし、売却後は基本的に退去が必要で、信用情報にも影響を与えるため、その後の住宅確保や融資利用に制約が生じます。
リースバックは、住宅ローンを完済できる場合に限られますが、居住継続が可能で信用情報への影響もありません。ただし、オーバーローンの状態では利用できないため、任意売却の方が適している場合があります。
最近では、任意売却とリースバックを組み合わせたサービスも登場しており、債務整理を行いながら住み続けることができる選択肢も増えています。この場合、第三者が物件を購入し、それを賃貸として利用する形態となります。
リースバックで後悔しないための7つの重要チェックポイント

リースバック契約を成功させるためには、契約前の十分な検討と準備が不可欠です。安易な判断による契約は、後々の生活に大きな影響を与える可能性があります。
ここでは、リースバック契約において必ず確認すべき7つの重要なチェックポイントを、専門家の視点から解説します。これらのポイントを確認することで、安心してリースバックを利用できるでしょう。
① 賃貸契約は「普通借家」か「定期借家」か
最も重要な確認事項は、賃貸借契約の種類です。「普通借家契約」と「定期借家契約」では、住み続けられる期間や更新条件が大きく異なります。
普通借家契約の場合、貸主からの更新拒絶には正当な理由が必要で、借主が希望すれば基本的に契約更新が可能です。一方、定期借家契約では、契約期間満了時に自動的に契約が終了し、更新はできません。
多くの事業者は定期借家契約を採用する傾向があり、契約期間は2〜3年程度に設定されることが多いです。この場合、期間満了時には必ず退去しなければなりません。長期間住み続けることを希望する場合は、普通借家契約を選択できる事業者を探すか、定期借家契約でも再契約の可能性について事前に確認しておきましょう。
② 家賃は適正な水準か
家賃の設定根拠と金額の妥当性を慎重に検討することが重要です。リースバックの家賃は、売却価格に対して年率8〜13%程度で設定されることが多く、周辺の賃貸相場より高めになる傾向があります。
複数の事業者から見積もりを取得し、家賃水準を比較検討しましょう。また、周辺地域の同等物件の賃貸相場も調査し、極端に高い設定になっていないかを確認することが大切です。
家賃の改定条件についても確認が必要です。契約期間中の家賃据え置きなのか、定期的な見直しがあるのかによって、長期的な負担が大きく変わります。インフレや周辺相場の変動による家賃上昇リスクも考慮に入れて、支払い能力の範囲内であることを確認しましょう。
③ 買戻しに関する条件(価格・期間)は明確か
買戻しオプションがある場合は、その条件を詳細に確認することが重要です。買戻し価格の算定方法、買戻し可能期間、手続きの流れなどを明確にしておきましょう。
買戻し価格は、通常は売却価格の110〜130%程度に設定されますが、事業者によって算定方法が異なります。固定価格なのか、経過年数に応じた計算式があるのかを確認し、将来の資金計画に組み込むことが大切です。
買戻し可能期間についても、契約締結から何年以内なのか、どのタイミングで買戻しの意思表示をする必要があるのかを把握しておきましょう。期間を過ぎてしまうと買戻しができなくなるため、計画的な資金準備が必要です。
④ 修繕費用の負担区分はどちらになっているか
物件の修繕費用の負担区分は、月々の実質負担額に大きく影響します。通常の賃貸借契約では、構造部分の修繕は貸主負担、設備の軽微な修繕は借主負担となることが多いです。
リースバック契約では、事業者によって費用負担の区分が異なるため、契約書で詳細に確認することが重要です。特に、築年数が古い物件の場合は、設備の故障や修繕が頻繁に発生する可能性があります。
エアコンや給湯器などの設備交換、外壁や屋根の修繕、水回りの修理などの費用負担について、具体的な金額の取り決めがあるかも確認しましょう。予想外の修繕費負担により、月々の生活費が圧迫される可能性を事前に把握しておくことが大切です。
⑤ 契約書の内容を十分に理解できているか
リースバック契約は、売買契約と賃貸借契約の二つの契約書を同時に締結します。それぞれの契約書の内容を十分に理解し、不明な点があれば必ず質問することが重要です。
特に、契約解除の条件、違約金の設定、敷金・礼金の有無、契約更新の条件などは、後々トラブルになりやすい項目です。法律用語が多く理解が困難な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
契約書に記載されていない口約束は、後で問題になることがあります。重要な条件については、必ず書面で確認し、契約書に反映されていることを確認しましょう。契約前に十分な時間をかけて内容を検討することが、後悔しない契約の鍵となります。
⑥ 複数の事業者を比較検討したか
リースバック事業者によって、売却価格、家賃、サービス内容が大きく異なります。最初に相談した事業者で決めてしまうのではなく、必ず複数の事業者から提案を受けることが重要です。
比較検討する際は、売却価格だけでなく、家賃の水準、契約期間、買戻し条件、修繕費負担、事業者の信頼性なども総合的に評価しましょう。また、担当者の対応や説明の丁寧さも、長期的な関係を築く上で重要な判断材料です。
事業者の財務状況や事業継続性も確認すべきポイントです。賃貸借契約は長期間続くため、事業者が途中で経営困難になった場合のリスクも考慮に入れる必要があります。業界での実績や口コミ、財務諸表の公開状況なども参考にしましょう。
⑦ 買戻しができない場合のリスクを許容できるか
買戻しオプションがあっても、将来的に買戻しができない可能性があります。経済状況の変化や健康状態の悪化により、買戻し資金を準備できない場合のリスクを事前に検討しておくことが重要です。
買戻しができない場合、契約期間満了時に退去が必要になる可能性があります。特に定期借家契約の場合は、必ず退去しなければなりません。高齢になってからの住み替えは、身体的・精神的な負担が大きいため、このリスクを許容できるかどうかを慎重に判断しましょう。
また、買戻しを前提とした生活設計ではなく、賃貸として住み続けることを基本とした計画を立てることも重要です。買戻しはオプションとして考え、できない場合でも生活に支障がないような準備をしておくことが賢明です。
リースバックの仕組みに関するよくある質問(Q&A)

リースバックについて多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。利用を検討される際の参考にしてください。
住宅ローンが残っていてもリースバックは利用できますか?
住宅ローンが残っている場合でも、売却価格で完済できればリースバックの利用は可能です。ただし、残債額が物件価値を上回っている場合(オーバーローン)は、基本的に利用できません。
リースバック事業者は、査定時に住宅ローンの残債額も含めて検討します。売却価格から残債を差し引いた金額が手元に残るため、事前に残債額を正確に把握しておくことが重要です。
オーバーローンの場合は、任意売却や債務整理を検討する必要があります。最近では、任意売却とリースバックを組み合わせたサービスも登場しているため、専門家に相談してみることをお勧めします。
家賃はどのようにして決まるのですか?
家賃は主に売却価格を基準として決定されます。一般的には、売却価格に対して年率8〜13%程度の利回りで設定されることが多く、これを12で割った金額が月額家賃となります。
例えば、2000万円で売却した物件の場合、年利10%とすると年間200万円、月額約16万7千円の家賃となります。ただし、物件の立地や築年数、周辺相場なども考慮されるため、事業者によって設定方法が異なります。
家賃の妥当性を判断するためには、周辺の賃貸相場と比較することが重要です。極端に高い設定になっていないかを確認し、複数の事業者から見積もりを取得することをお勧めします。
事業用の物件(店舗や事務所)も対象になりますか?
多くのリースバック事業者では、住宅だけでなく事業用物件も取り扱っています。店舗兼住宅、事務所、工場などの事業用物件でもリースバックの利用が可能です。
事業用物件の場合、事業の継続性や収益性も評価の対象となります。また、用途地域や建築基準法などの法規制についても、住宅以上に詳細な確認が必要です。
ただし、事業用物件を扱う事業者は限られているため、事前に対応可能かどうかを確認することが重要です。事業用物件の場合は、住宅以上に専門的な知識が必要となるため、経験豊富な事業者を選ぶことが大切です。
途中で家賃が払えなくなったら、すぐに退去しないといけませんか?
家賃の支払いが滞った場合でも、すぐに退去を求められることはありません。通常の賃貸借契約と同様に、まずは催促が行われ、一定期間経過後に契約解除の手続きが進められます。
一般的には、2〜3ヶ月程度の滞納が続いた場合に契約解除の対象となることが多いです。ただし、事業者や契約内容によって異なるため、契約書で確認しておくことが重要です。
支払いが困難になった場合は、早めに事業者に相談することをお勧めします。支払い条件の変更や分割払いなど、解決策を検討してもらえる可能性があります。問題を先延ばしにすると、選択肢が限られてしまうため、早期の対応が大切です。
相談から資金を受け取るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
リースバックの場合、相談から資金受け取りまでの期間は、通常1〜2ヶ月程度となります。これは通常の不動産売却と比較して短期間で、迅速な資金調達が可能です。
具体的な流れとしては、相談・査定に1週間程度、条件提示・交渉に1〜2週間程度、契約締結に1週間程度、決済まで1〜2週間程度が目安となります。
ただし、住宅ローンの残債確認や権利関係の調査に時間を要する場合、書類の準備が遅れる場合などは、期間が延びることもあります。急ぎの場合は、事前に必要書類を準備し、スケジュールを確認しておくことが重要です。
まとめ:リースバックは仕組みの正しい理解と慎重な検討が成功の鍵
リースバックは、住み慣れた自宅を手放すことなく資金調達ができる有効な手段です。しかし、所有権の喪失や継続的な家賃負担など、慎重に検討すべき側面も存在します。
成功の鍵は、仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に適しているかどうかを冷静に判断することです。メリットだけでなくデメリットも十分に把握し、長期的な生活設計の中で検討することが重要です。
不明な点や不安な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。リースバックは人生の重要な選択の一つです。十分な情報収集と慎重な検討により、最適な判断を行ってください。

