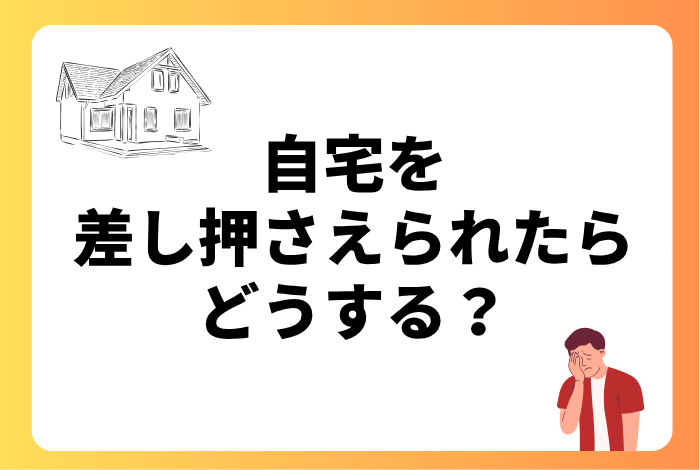
住宅ローンの支払いが困難になり、「家を差し押さえられるかもしれない」という不安を抱えている方は決して珍しくありません。新型コロナウイルスの影響や物価高騰により、多くの方が同じような状況に直面しています。
この記事では、差し押さえから競売までの具体的な流れと、各段階でどのような手続きが行われるのかを詳しく解説します。また、まだ間に合う回避策についても具体的な方法をご紹介していきます。
そもそも「家の差し押さえ」とは?
家の差し押さえとは、住宅ローンなどの返済が滞った場合に、債権者(銀行など)が裁判所に申し立てを行い、債務者の不動産を強制的に売却する手続きの第一歩です。
具体的には、債務者が所有する不動産に対して法的な拘束力を持つ「差押登記」が行われます。これにより、債務者は勝手に不動産を売却したり、担保に入れたりすることができなくなります。
給与差し押さえとの違いは、給与の場合は毎月の一定額が継続的に差し押さえられるのに対し、不動産の差し押さえは最終的に競売による売却を目的としている点です。
差し押さえ自体は売却の前段階であり、この時点ではまだ家に住み続けることができます。しかし、何も対策を取らなければ、最終的に競売により強制的に売却され、立ち退きを余儀なくされることになります。
【時間との勝負】住宅ローン滞納から家の差し押さえ、競売までの流れと期間

住宅ローンの滞納から実際に家を失うまでには、法的に定められた手順があります。この流れを理解することで、どの段階で何をすべきかが明確になり、適切なタイミングで対策を講じることができます。
各段階の期間は金融機関や債務者の状況により多少の違いはありますが、一般的な目安として参考にしてください。早めの対応が解決への近道となります。
STEP1:住宅ローンの滞納(1~2ヶ月)
住宅ローンの支払いが遅れると、まず金融機関から電話や書面による連絡が入ります。この段階では、まだ「うっかり忘れ」程度の扱いとなり、数日から1週間程度の遅延であれば大きな問題にはなりません。
しかし、1ヶ月以上の滞納が続くと、金融機関内部で「要注意債務者」として扱われ始めます。この時点で担当者から支払い計画についての相談を持ちかけられることもあります。
2ヶ月目に入ると、より積極的な連絡が入るようになります。この段階で正直に現状を説明し、返済計画の見直しを相談することで、リスケジュール(返済条件の変更)が認められる可能性があります。
STEP2:督促状・催告書が届く(3~6ヶ月)
滞納が3ヶ月を超えると、金融機関から正式な督促状が送付されます。この書面には、滞納額と支払い期限が明記されており、「このまま滞納が続くと法的措置を取る」旨の警告が記載されています。
4~5ヶ月目になると、より厳しい内容の催告書が届くようになります。この段階では、単なる督促ではなく、「期限の利益の喪失」について言及されることが多くなります。
6ヶ月近くになると、保証会社による代位弁済の準備が本格化します。この時点で債権者が銀行から保証会社に移り、より厳格な債権回収が始まることになります。
STEP3:期限の利益の喪失通知が届く
住宅ローンの滞納が続くと、金融機関から「期限の利益の喪失通知」が送付されます。これは、「分割払いの権利を失い、残債を一括で返済する必要がある」ことを意味する重要な通知です。
通常、住宅ローンは20年や30年といった長期間にわたって分割返済する契約になっています。しかし、約定通りの返済が行われなくなると、この分割払いの権利(期限の利益)を失うことになります。
この通知が届いた時点で、数千万円の住宅ローン残債を一括で返済する義務が発生します。当然、多くの債務者にとって一括返済は現実的ではないため、この段階で保証会社による代位弁済が行われ、競売申立ての準備が本格化します。
STEP4:【差押通知】競売開始決定通知書が届く(6~8ヶ月)
保証会社による代位弁済が完了すると、裁判所から「競売開始決定通知書」が送付されます。この通知により、正式に不動産の差し押さえが決定し、競売手続きが開始されることになります。
同時に、不動産の登記簿に「差押登記」が行われます。この登記により、債務者は勝手に不動産を売却することができなくなり、第三者に対しても差し押さえの事実が明らかになります。
通知書には、競売を申し立てた債権者名、債権額、担当裁判所などが記載されています。この段階になると、競売を止めるためには債権者との直接交渉や任意売却などの積極的な対応が必要となります。
STEP5:裁判所による現況調査(8~9ヶ月)
競売開始決定後、裁判所から執行官と不動産鑑定士が物件の現況調査を行います。この調査は、競売での売却価格を決定するための重要な手続きです。
調査では、建物の状態、居住の有無、占有者の確認、近隣環境などが詳細に調べられます。債務者が在宅している場合は、協力的に対応することが重要です。拒否することはできません。
この調査結果に基づいて、裁判所は「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の3点セットを作成します。これらの資料は競売入札の際に買受希望者に公開され、売却価格の判断材料となります。
STEP6:期間入札の通知と競売開始(10~12ヶ月)
現況調査の完了後、裁判所から「期間入札の通知」が送付されます。この通知には、入札期間、開札日、売却基準価額などが記載されており、いよいよ競売の最終段階に入ります。
期間入札期間は通常1週間程度設定され、この期間中に購入希望者が入札を行います。入札は一般に公開されており、誰でも参加可能です。
売却基準価額は、鑑定評価額の7割程度に設定されることが多く、市場価格よりもかなり安い価格での売却となります。この段階でも任意売却による解決は可能ですが、時間的な制約が厳しくなります。
STEP7:開札・売却、そして立ち退き
入札期間終了後、裁判所で開札が行われ、最高額で入札した者が落札者となります。落札者は落札価格を裁判所に納付し、所有権移転の手続きが行われます。
売却が成立すると、新しい所有者から立ち退きの要求が行われます。任意に立ち退かない場合は、強制執行により物理的に退去させられることになります。
競売での売却価格は市場価格の5~7割程度となることが多く、住宅ローンの残債が完全に消えることは稀です。残った債務については、引き続き返済義務が残ることになります。
家の差し押さえで起こる5つのこと|生活・家族・信用情報への影響

家の差し押さえが実行されると、単に住む場所を失うだけではなく、生活全般にわたって深刻な影響が及びます。これらの影響を事前に理解しておくことで、早期の対策の重要性がより明確になります。
以下では、差し押さえによる具体的な影響について、実際に起こりうる事例を交えながら詳しく解説していきます。
①最終的には家からの立ち退きが強制執行される
競売が成立すると、新しい所有者から立ち退きの要求が行われます。多くの場合、まず書面による退去要求が送付され、3ヶ月程度の猶予期間が設けられます。
しかし、この期間内に任意に退去しない場合、裁判所による強制執行が行われます。執行官と業者が自宅に来て、家財道具を搬出し、鍵を交換されてしまいます。
強制執行の費用は元の所有者(債務者)が負担することになり、通常50万円から100万円程度かかります。また、搬出された家財道具の保管費用も別途発生し、引き取りに行かなければ処分されてしまいます。
②競売の事実はご近所や会社に知られる可能性がある
競売の情報は、裁判所の掲示板やインターネットの競売情報サイトで公開されます。物件の住所、間取り、写真なども含まれているため、近隣住民や知人に知られる可能性があります。
また、現況調査の際には裁判所関係者が自宅を訪問するため、近所の方に不審に思われることもあります。競売の入札期間中は、購入希望者が物件を見学に来ることもあります。
会社に直接連絡が行くことはありませんが、同僚や上司が偶然競売情報を目にしたり、住所変更の手続きから推測されたりする可能性もあります。
③ブラックリストに登録され、新たな借入やカード作成が困難になる
住宅ローンの長期滞納により、個人信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に延滞情報が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト」の状態で、5~10年間は記録が残ります。
この状態では、新たな住宅ローンの借入はもちろん、自動車ローンやクレジットカードの作成、携帯電話の分割払いなども困難になります。
賃貸住宅を借りる際も、保証会社の審査で不利になる可能性があります。家族がローンを組む際の連帯保証人になることも難しくなるため、生活全般に長期的な影響を与えます。
④競売で売れても住宅ローンが残るケースが多い(残債)
競売での売却価格は、市場価格の5~7割程度となることが一般的です。そのため、住宅ローンの残債が完全に消えることは稀で、多くの場合で数百万円から数千万円の債務が残ります。
例えば、住宅ローン残債が3000万円の物件が競売で1500万円で売却された場合、1500万円の残債が継続します。この残債は無担保債務となり、債権者から分割返済を求められます。
残債の返済が困難な場合は、自己破産や個人再生などの債務整理を検討する必要があります。競売後の生活再建においても、この残債の処理が重要な課題となります。
⑤連帯保証人へ一括請求がいく
住宅ローンに連帯保証人が設定されている場合、主債務者が返済不能になると、保証会社から連帯保証人に対して一括返済の請求が行われます。
連帯保証人は主債務者と同等の責任を負うため、「知らなかった」「同意していない」といった理由で支払いを拒否することはできません。
親族が連帯保証人になっている場合が多く、家族関係に深刻な影響を与える可能性があります。連帯保証人も返済困難な場合は、同様に債務整理を検討する必要があります。
まだ間に合う!家の差し押さえを回避する3つの現実的な方法

家の差し押さえが決定されても、競売の開札まではまだ時間があります。この期間を有効活用することで、より良い条件での解決が可能になります。
以下では、差し押さえを回避するための具体的な方法について、それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説します。状況に応じて最適な選択肢を検討してください。
解決策①:任意売却|市場価格に近い値段で家を売却する
任意売却は、競売になる前に債権者の同意を得て、一般市場で不動産を売却する方法です。競売と比較して多くのメリットがあり、差し押さえ回避の最も現実的な選択肢として広く活用されています。
競売より高く売れる可能性
任意売却では、市場価格の8~9割程度での売却が期待できます。競売の5~7割と比較すると、数百万円から数千万円も高く売れる可能性があります。
高く売れることで住宅ローンの残債を大幅に減らすことができ、売却後の生活再建がより容易になります。また、引越し費用などの諸費用を売却代金から捻出できる場合もあります。
専門の不動産会社が市場調査を行い、適正価格での売却活動を行うため、競売よりも確実に高値での売却が期待できます。
周囲に知られずに売却を進められる
任意売却は通常の不動産売却と同じ手続きで進められるため、競売のように情報が公開されることはありません。近隣住民や知人に事情を知られることなく売却を進めることができます。
購入希望者の内覧も、通常の売却と同様に事前予約制で行われるため、不特定多数の人が物件を見学に来ることもありません。
プライバシーが保護されることで、精神的な負担が軽減され、売却後の生活再建にも良い影響を与えます。
引っ越し時期や費用を交渉できる
任意売却では、買主との交渉により引っ越し時期を調整することが可能です。子供の転校時期や仕事の都合に合わせて、無理のないスケジュールで進めることができます。
また、売却代金の一部を引っ越し費用として確保できる場合もあります。債権者との交渉により、50万円から100万円程度の費用を認めてもらえることがあります。
競売の場合は強制的な立ち退きとなりますが、任意売却では計画的な引っ越しが可能になります。
解決策②:個人再生|家を残せる可能性はあるが条件が厳しい
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、債務を大幅に減額してもらう法的手続きです。住宅ローン特例を利用することで、家を残しながら他の借金を整理できる可能性があります。
ただし、住宅ローン自体の減額はできないため、住宅ローンの返済は継続する必要があります。また、安定した収入があることが前提となり、手続きも複雑で時間がかかります。
個人再生が成功しても、住宅ローンの滞納分は解消する必要があり、現実的には相当な収入回復が必要です。専門家である弁護士や司法書士との相談が必須となります。
解決策③:自己破産|借金はなくなるが家は手放すことになる
自己破産は、すべての財産を処分する代わりに、借金を帳消しにしてもらう法的手続きです。住宅ローンも含めてすべての債務が免責されるため、経済的には最も効果的な解決方法です。
しかし、自己破産では原則として20万円を超える財産は処分対象となるため、家を手放すことは避けられません。また、一定期間は職業制限もあり、生活に制約が生じます。
自己破産後は信用情報に記録が残るため、7~10年程度は新たな借入が困難になります。しかし、借金からは完全に解放されるため、人生の再スタートを切ることができます。
状況別|家の差し押さえに関する悩みはどこに相談すべき?

家の差し押さえという深刻な問題に直面した際、「誰に相談すればよいのか」「どこから手をつければよいのか」迷われる方も多いでしょう。相談先によって得られる解決策や進め方が大きく異なるため、現在の状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
以下では、それぞれの専門家が提供できるサービスと、どのような状況の時に相談すべきかを具体的に解説します。
弁護士・司法書士:法的な手続き全般を任せたい場合
弁護士や司法書士は、差し押さえに関する法的手続き全般を代行してくれます。債権者との交渉、裁判所への申立て、個人再生や自己破産などの債務整理手続きなど、幅広い対応が可能です。
特に、すでに裁判所から競売開始決定通知が届いている場合や、複数の債権者から同時に請求を受けている場合には、法的な専門知識が必要となります。
相談料は30分5000円程度が相場で、債務整理を依頼する場合は着手金20万円~50万円程度が必要です。法テラスの利用により、費用を抑えた相談も可能です。
不動産会社(任意売却専門):任意売却を具体的に進めたい場合
任意売却を専門とする不動産会社は、債権者との交渉から実際の売却活動まで、任意売却に関する全ての手続きを代行します。通常の不動産売却と異なり、債権者との調整が必要なため、専門知識が重要です。
市場価格の査定、販売戦略の立案、買主との交渉、引っ越し時期の調整など、売却に関する実務的な対応を総合的に行います。
多くの場合、相談料は無料で、成功報酬として売却価格の3%程度を債権者が負担するため、依頼者の負担は最小限に抑えられます。
金融機関(借入先):返済計画の見直しを相談したい初期段階の場合
住宅ローンの返済が困難になった初期段階では、まず借入先の金融機関に相談することが重要です。返済条件の変更(リスケジュール)により、一時的に返済額を減らしたり、返済期間を延長したりできる場合があります。
金融機関では、収入減少の理由や今後の見通しを詳しく聞き取り、現実的な返済計画を一緒に検討してくれます。早期に相談することで、より柔軟な対応が期待できます。
ただし、すでに長期間滞納している場合や、保証会社による代位弁済が行われた後では、金融機関での解決は困難になります。
【注意】家の差し押さえ前後に絶対やってはいけないこと

家の差し押さえという非常事態に直面すると、パニック状態になり、冷静な判断ができなくなることがあります。しかし、誤った行動を取ることで状況がさらに悪化し、解決の選択肢を狭めてしまう可能性があります。
以下では、差し押さえ前後に絶対に避けるべき行動について、その理由と想定される結果を詳しく解説します。
督促状や裁判所からの通知を無視する
金融機関からの督促状や裁判所からの通知を無視することは、状況を悪化させる最も危険な行動です。これらの書面には法的な効力があり、無視することで手続きが自動的に進行してしまいます。
特に裁判所からの通知には、異議申立てや意見書提出の期限が設けられていることが多く、この期限を過ぎると不利な条件での手続きが確定してしまいます。
「怖くて開封できない」「どうせ払えないから意味がない」という気持ちは理解できますが、現状を正確に把握するためにも、すべての書面に目を通し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
夜逃げをする
借金や差し押さえから逃れるために夜逃げをすることは、根本的な解決にはなりません。債務は消えることがなく、むしろ遅延損害金により債務額が増加し続けます。
また、住民票を移さずに転居すると、重要な通知が届かなくなり、知らないうちに手続きが進行してしまう可能性があります。就職や子供の転校などの際にも、正常な手続きが困難になります。
夜逃げによる精神的・経済的な負担は非常に大きく、家族にも深刻な影響を与えます。どんなに困難な状況でも、正面から向き合い、適切な解決策を探すことが重要です。
新たな借金で返済しようとする
住宅ローンの返済のために消費者金融やクレジットカードでキャッシングを行うことは、問題を深刻化させる危険な行動です。高金利の借入により、総債務額が急速に増加してしまいます。
また、親族や知人からの借入で一時的に返済を続けても、根本的な収入改善がなければ、より多くの人を巻き込んだ深刻な事態に発展する可能性があります。
「とりあえず今月だけ」という考えで始めた借入が、最終的には自己破産しか選択肢がない状況まで追い込まれるケースも少なくありません。返済困難な状況では、借入による先延ばしではなく、根本的な解決策を検討することが重要です。
まとめ:家の差し押さえは回避できる可能性も。一人で悩まず、まずは専門家へ相談を
家の差し押さえは確かに深刻な問題ですが、適切な対策を取ることで回避できる可能性が十分にあります。重要なのは、早期に現状を把握し、専門家のアドバイスを受けながら最適な解決策を見つけることです。
住宅ローンの滞納から競売まで約1年程度の時間があるため、この期間を有効活用することで、競売よりも有利な条件での解決が可能になります。任意売却であれば市場価格に近い値段での売却が期待でき、プライバシーも保護されます。
一人で悩み続けることで時間だけが過ぎ、選択肢が狭まってしまいます。弁護士、司法書士、任意売却専門の不動産会社など、状況に応じた専門家への相談を躊躇することなく、できるだけ早期に行動を起こすことが解決への第一歩となります。

