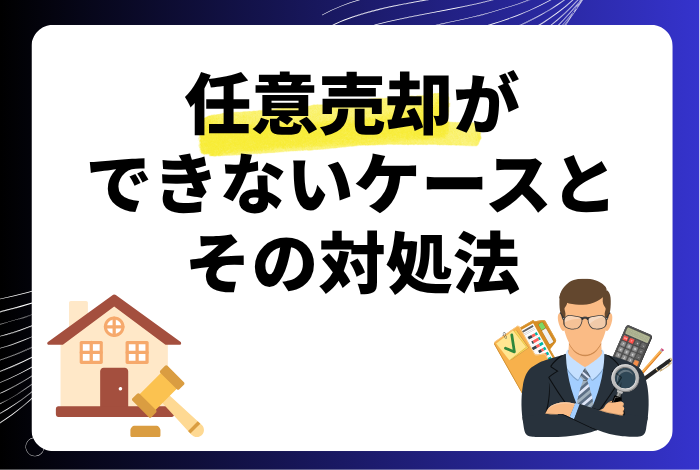
住宅ローンの返済が困難になると、多くの方が「家を手放さなければならない」という現実に直面します。そんな時、「任意売却」という選択肢を検討される方は少なくありません。
実際、任意売却は競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、引越し費用の捻出や新生活への準備時間を確保できるなど、債務者にとって有利な選択肢です。ところが、すべてのケースで実現できるわけではありません。
この記事では、任意売却ができない代表的な9つのケースと、それぞれの対処法について詳しく解説します。現在のご自身の状況と照らし合わせながら、最善の解決策を見つけるための参考にしてください。
任意売却とは?競売との違いと「できない」と言われる理由

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者(金融機関)の同意を得て不動産を売却する方法です。競売とは異なり、市場価格に近い価格での売却が期待でき、売却時期をある程度調整できるメリットがあります。
競売の場合、裁判所が強制的に売却を進めるため、市場価格の6~7割程度の価格になることが一般的です。一方、任意売却では通常の不動産売買と同様に売却活動を行うため、より高い価格での売却が可能になります。
しかし、任意売却を実現するためには、債権者をはじめとする関係者全員の同意が必要です。また、税金の滞納状況や時間的制約など、様々な条件をクリアしなければなりません。
これらの条件を満たせない場合、「任意売却ができない」という結果になってしまいます。つまり、任意売却は債務者にとって有利な選択肢である一方で、実現には高いハードルが存在するのが現実なのです。
【状況別】任意売却ができない代表的な9つのケース
任意売却ができない理由は、大きく分けて「関係者の同意」「金融機関の同意」「滞納・差押え」「時間的制約」「売却活動」「契約上の問題」「依頼先の問題」の7つの要因に分類できます。
以下では、実際によく発生する9つのケースについて、なぜ任意売却ができないのかという理由と、まず何をすべきかという初期対応を具体的に解説します。ご自身の状況に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
ケース1:【関係者の同意】連帯保証人の同意が得られない
住宅ローンの契約で連帯保証人が設定されている場合、任意売却には連帯保証人の同意が不可欠です。連帯保証人は債務者と同等の返済責任を負っているため、売却による残債の処理について納得していただく必要があります。
連帯保証人が同意しない理由として、売却後の残債について十分な説明を受けていない、または感情的な対立が生じているケースが多く見られます。特に親族が連帯保証人になっている場合、家族間の複雑な感情が影響することも少なくありません。
この場合の初期対応として、まずは連帯保証人に対して現在の状況を正直に説明し、任意売却のメリットを理解してもらうことが重要です。ご自身で伝えるよりも、本人に代わって弁護士や任意売却の専門家が客観的な立場から説明することで、感情的な対立を避けながら冷静な判断を促すことができます。
ケース2:【関係者の同意】共有名義人(夫婦・親子など)の同意が得られない
不動産が共有名義になっている場合、名義人全員の同意なしに任意売却を進めることはできません。特に夫婦共有名義の場合、離婚協議中であったり、既に別居していたりすると、話し合いが困難になることがあります。
親子間の共有名義では、親が認知症になってしまい意思表示ができない状況や、相続時に兄弟姉妹で共有名義になったものの、意見が分かれてしまうケースもあります。
このような状況では、まず共有名義人全員で話し合いの場を設けることが必要です。感情的な対立がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に仲介を依頼することを検討しましょう。また、親の認知症など意思能力に問題がある場合は、成年後見制度の利用も視野に入れる必要があります。
ケース3:【金融機関の同意】債権者(銀行など)が売却価格に納得しない
任意売却では、債権者が売却価格に納得しなければ実行できません。債権者は少しでも多くの債権を回収したいと考えているため、売却価格が相場より大幅に安い場合は同意してもらえない可能性があります。
また、債権者が任意売却に応じる条件として、「ハンコ代」と呼ばれる抵当権抹消費用や、引越し費用の一部を売却代金から捻出することを求められる場合もあります。これらの費用を考慮した売却価格でなければ、債権者の同意を得ることは困難です。
この場合は、不動産の適正な市場価格を正確に把握し、債権者に対して合理的な売却価格を提示することが重要です。複数の不動産会社に査定を依頼し、価格の妥当性を客観的に示すことで、債権者との交渉を有利に進めることができます。
ケース4:【滞納・差押え】税金(固定資産税など)の滞納額が多すぎる
固定資産税や住民税などの税金を滞納している場合、役所が不動産に対して差押えを行うことがあります。差押えが実行されると不動産の処分ができなくなるため、任意売却を行うためには差押えを解除してもらう必要があります。
税金の滞納額が多額になっている場合、売却代金だけでは完済できず、差押えの解除に応じてもらえない可能性があります。また、役所との交渉が必要になるため、手続きが複雑化し、時間もかかってしまいます。
まずは役所の納税課などに相談し、滞納額の正確な把握と分割納付の可能性を確認することが重要です。場合によっては、売却代金の一部を税金の支払いに充当することで、差押えの解除に応じてもらえることもあります。早めに専門家に相談し、役所との交渉を進めることをお勧めします。
ケース5:【滞納・差押え】マンションの管理費・修繕積立金を滞納している
マンションの管理費や修繕積立金を滞納している場合、管理組合が不動産に対して先取特権を行使する可能性があります。これにより、買主が滞納分を負担することになったり、売却手続きが複雑化したりするリスクがあります。
また、滞納額が多額になっている場合、管理組合が任意売却に反対することもあります。管理組合としては、確実に滞納分を回収したいと考えているため、競売による配当を期待することがあるのです。
この場合は、管理組合と直接交渉し、売却代金から滞納分を優先的に支払うことで合意を得る必要があります。管理会社や管理組合の理事会に対して、任意売却のメリットを説明し、協力を求めることが重要です。専門家を介して交渉することで、よりスムーズな解決が期待できます。
ケース6:【時間的制約】競売の入札が開始されてしまっている

競売の手続きが進んでしまい、入札が開始されると、任意売却の時間的余裕がほとんどなくなってしまいます。競売の入札期間は通常1週間程度であり、開札日の前日まで任意売却は可能ですが、現実的には非常に困難です。
競売の入札開始後は、買主を見つけて売買契約を締結し、決済までを短期間で完了させなければなりません。また、競売の落札者が現れた場合、任意売却の価格がそれを上回らなければ債権者の同意を得ることは困難です。
この段階では、時間との勝負になります。直ちに任意売却の専門家に相談し、緊急的な対応を取る必要があります。場合によっては、競売の取り下げを債権者に申し立てることも検討する必要があります。ただし、これらの手続きは専門的な知識が必要なため、必ず専門家に依頼することをお勧めします。
ケース7:【売却活動】期間内に買主が見つからない
任意売却には時間制限があるため、期間内に買主が見つからない場合は競売へと移行してしまいます。債権者が設定する売却期間は通常3~6ヶ月程度であり、この期間内に売却を完了させなければなりません。
買主が見つからない理由として、売却価格が相場より高く設定されている、物件の状態が悪い、立地条件が良くない、などが考えられます。また、売却活動を行う不動産会社の営業力や販売ネットワークが不十分な場合もあります。
この場合は、まず売却価格の見直しを検討する必要があります。市場動向を踏まえた適正価格での売却を行うことで、買主が見つかる可能性が高まります。また、複数の不動産会社に依頼したり、任意売却の実績が豊富な専門会社に変更したりすることも有効です。
ケース8:【契約上の問題】売却後の残債の返済計画が立てられない
任意売却を行っても住宅ローンが完済できない場合、残債の返済計画について債権者と合意する必要があります。債権者は、債務者の収入状況や返済能力を審査し、現実的な返済計画かどうかを判断します。
債務者の収入が不安定であったり、他の借入れが多額であったりする場合、返済計画の合意が困難になることがあります。また、債権者によっては、残債の返済について保証人を求められる場合もあります。
この場合は、まず自身の収入状況を正確に把握し、現実的な返済計画を作成することが重要です。必要に応じて、債務整理の専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切な返済計画を立てることをお勧めします。場合によっては、個人再生や自己破産などの法的手続きを検討することも必要になるかもしれません。
ケース9:【依頼先の問題】信頼できない任意売却業者に依頼している
任意売却を専門としない一般の不動産会社に依頼した場合、債権者との交渉ノウハウが不足しているため、手続きが進まないことがあります。また、高額なコンサルティング料を要求する悪質な業者も存在するため、注意が必要です。
信頼できない業者の特徴として、契約前に費用を要求する、債権者との交渉経験が乏しい、説明が曖昧で具体的なスケジュールを示さない、などが挙げられます。このような業者に依頼してしまうと、任意売却の成功確率が大幅に低下してしまいます。
この場合は、速やかに依頼先を変更することを検討する必要があります。任意売却の実績が豊富で、債権者との交渉経験が豊富な専門家を選ぶことが重要です。
任意売却ができないかも…その場合の3つの対処法

任意売却ができない状況に直面した場合でも、決して諦める必要はありません。適切な対処法を取ることで、競売を回避したり、より良い条件で債務整理を進めたりすることが可能です。
以下では、任意売却が困難な場合に検討すべき3つの対処法について詳しく解説します。いずれの方法も専門的な知識が必要なため、必ず専門家に相談することをお勧めします。
対処法1:まずは専門家へ相談し、状況を正確に把握する
任意売却ができないと判断する前に、まずは専門家に相談することが重要です。自己判断では困難に思えるケースでも、専門家の知識と経験により解決策が見つかることがあります。
相談先としては、任意売却を専門とする不動産会社、弁護士、司法書士、税理士などが挙げられます。それぞれの専門分野により得意とする分野が異なるため、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。
例えば、債権者との交渉が必要な場合は任意売却専門の不動産会社、法的な手続きが必要な場合は弁護士、税金の滞納が問題となっている場合は税理士に相談するのが効果的です。多くの専門家が初回相談を無料で行っているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
対処法2:個人再生や自己破産など、他の債務整理を検討する
任意売却が不可能な場合、個人再生や自己破産などの法的な債務整理手続きを検討することも一つの解決策です。これらの手続きを行うことで、競売を回避し、債務を整理することが可能になります。
個人再生は、住宅ローン以外の債務を大幅に減額し、住宅を維持しながら返済を続けることができる制度です。ただし、住宅ローンの返済は継続する必要があるため、安定した収入が必要になります。
自己破産は、すべての債務を免責してもらう制度ですが、住宅は手放すことになります。しかし、競売よりも手続きが迅速であり、新生活への移行を早めることができるメリットがあります。これらの手続きは弁護士に依頼することで、適切に進めることができます。
対処法3:リースバックを検討する
住み続けることを強く希望する場合、リースバックという選択肢もあります。リースバックとは、不動産を投資家に売却した後、賃貸として住み続けることができる制度です。
リースバックを利用することで、住環境を変えることなく、住宅ローンの問題を解決することができます。また、将来的に買い戻すことも可能な場合があります。ただし、売却価格が市場価格より低くなることが多く、賃料の支払いが継続的に発生することに注意が必要です。
リースバックを提供する会社は限られており、すべての物件が対象となるわけではありません。また、債務者の収入状況や物件の条件によっては利用できない場合もあります。リースバックを検討する場合は、複数の会社に相談し、条件を比較検討することが重要です。
任意売却を成功させるために最も重要なポイント

任意売却を成功に導くためには、適切なタイミングでの行動と、信頼できる専門家の選択が不可欠です。多くの方が「もう少し様子を見てから」と判断を先延ばしにしがちですが、時間が経過するほど選択肢は狭まってしまいます。
以下では、任意売却の成功確率を高めるための最も重要な2つのポイントについて解説します。
ポイント1:「早めの相談」が選択肢を広げる
任意売却の成功確率を高める最も重要な要素は、早めの相談です。住宅ローンの返済が厳しくなってきた段階、できれば滞納が始まる前に専門家に相談することで、より多くの選択肢を確保することができます。
滞納が始まってしまうと、債権者との交渉が厳しくなり、時間的な制約も生じます。一方、滞納前であれば、債権者も比較的柔軟な対応を示すことが多く、任意売却の条件交渉もスムーズに進む可能性があります。
また、早期の相談により、任意売却以外の解決策も検討することができます。例えば、借り換えやリスケジュールによる返済負担の軽減、親族からの援助による一時的な資金調達など、住宅を手放さずに済む方法が見つかる場合もあります。「まだ大丈夫」と思っている段階でも、一度専門家に相談してみることをお勧めします。
ポイント2:任意売却の実績が豊富な専門家を選ぶ
任意売却の成功は、依頼する専門家の能力に大きく左右されます。債権者との交渉経験が豊富で、任意売却の実績を多く持つ専門家を選ぶことが重要です。
実績豊富な専門家の特徴として、債権者ごとの特性や交渉のポイントを熟知している、販売活動のネットワークが充実している、各種手続きに精通しているなどが挙げられます。また、過去の成功事例を具体的に説明できることも、信頼できる専門家の証拠といえるでしょう。
専門家を選ぶ際は、任意売却の取扱件数や成功率、具体的な解決事例などを確認することが大切です。また、初回相談の際に、現在の状況に対する具体的な解決策を提示してもらえるかどうかも判断材料の一つです。費用についても事前に明確な説明を受け、納得できる条件で依頼することをお勧めします。
【まとめ】諦める前に、まずは信頼できる専門家へ相談を
任意売却ができない9つのケースについて解説してきましたが、いずれの場合も完全に解決策がないわけではありません。関係者の同意が得られない場合は専門家を介した交渉により解決の可能性があり、時間的制約がある場合でも迅速な対応により任意売却を実現できることがあります。
重要なのは、自己判断で諦めることなく、早い段階で適切な専門家に相談することです。住宅ローンの返済が困難になった時点で、できるだけ早く行動を起こすことが、より良い解決策につながります。
任意売却が困難な場合でも、個人再生や自己破産、リースバックなど、他の選択肢も存在します。これらの方法を含めて総合的に判断し、ご自身の状況に最も適した解決策を見つけることが大切です。
一人で悩みを抱え込まず、専門知識を持つプロフェッショナルの力を借りることで、必ず最善の道が見つかるはずです。現在住宅ローンの返済でお困りの方は、まずは信頼できる専門家への相談から始めてみてください。

